一般社団法人ケアと暮らしの編集社(以下、ケアくら)は、代表理事で医師でもある守本陽一さんが、社会における人とのつながりを処方することで生きがいやウェルビーイングを生み出す「社会的処方」を目指して設立した団体です。2016年からさまざまな事業を通して兵庫県豊岡市の地域の方々と交流し、「暮らしていたら自然と健康になるまちづくり」を進められています。
後編では、ケアくらに関わるスタッフの特徴や事業運営面の現状と難しさ、今後の展望について伺います。
前編はこちら:
プロフィール:守本陽一 氏
一般社団法人ケアと暮らしの編集社 代表理事
1993年、神奈川県生まれ、兵庫県養父市出身。医師。修士(芸術)。自治医科大学在学時から医療者が屋台を引いて街中を練り歩くYATAI CAFEや地域診断といったケアとまちづくりに関する活動を兵庫県但馬地域で行う。医師として働く傍ら、2020年11月に、一般社団法人ケアと暮らしの編集社を設立。図書館型地域共生・社会的処方拠点として、商店街の空き店舗を改修し、シェア型図書館、本と暮らしのあるところだいかい文庫をオープンし、運営している。重層的支援体制整備事業、社会的処方モデル事業等の自治体支援や民間企業との連携も行う。まちづくり功労者国土交通大臣表彰、グッドデザイン賞等受賞。共著に「ケアとまちづくり、ときどきアート(中外医学社)」「社会的処方(学芸出版社)」など。
医療系を中心にさまざまなスキルをもつスタッフが集まる
ーケアくらの活動拠点である兵庫県豊岡市は、都市部よりも人材獲得が難しい面もあるかと思いますが、どのような経緯で入社されるスタッフが多いのでしょうか?
ソーシャル・NPOなど専門の求人サイト経由で入社してくれた人もいますが、ほとんどは知り合いからの紹介や推薦です。スタッフには豊岡市に移住してもらって活動に参加してもらっています。
ーケアくらのスタッフは、専門的な知識を持っていたり専門職資格を持っている方が多いのでしょうか。また、運営に携わるスタッフに持っていてほしい資質はありますか?
もともと保健師をやっていた方やプレイワーカー(*1)をやっていた方など、さまざまな専門知識を持つ仲間が集まっており、それぞれが自分たちが何を大切にしていきたいのかを考えて取り組んでいます。
(*1)子どもの自由意志で自ら遊び育つ場所で専門的に従事している人(引用元:一般社団法人 日本プレイワーク協会 )
スタッフには、利用する方と「支援する側」「支援される側」という上下の関係ではなく横並びの関係にあることを大事にしつつ、リンクワーカーとして何か困りごとがあったときの繋ぎ先もわかっているという、両方の資質を持っていてほしいですね。
横並びになって本人のやりたいことのサポートをしつつ、本人への働きかけや必要な時に必要な機関へつなぐことも重要だと考えています。
ーリンクワーカーの役割について、より詳しく教えていただけますか。
リンクワーカーとは、人と場を繋ぐ役割をする人のことを指します。
医療機関や行政、地域の民生委員や相談員、NPOなど、フォーマルな機関からインフォーマルな機関まで幅広い地域・社会資源につなげることで、その人を見守るコミュニティを形成する役割を果たします。
こうした人とのつながりを処方することを、社会的処方と呼びます。社会的処方とは、薬ではなく人とのつながりを処方することで、社会的孤立を解消していこうという考え方のことです。
1980年頃にイギリスで誕生し、現在は日本でも孤立による不安や体調不良を解消するための考え方として取り入れられています。
健康というのは身体的なものだけでなく、社会的なつながりがあることなども指しており、孤立を解消するためのつながりをつくっていくのも必要な支援の一つと言えます。
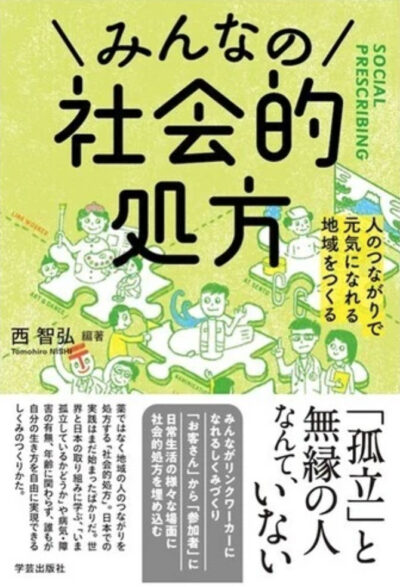
画像:共著として守本氏も執筆された『みんなの社会的処方』
組織基盤
ーテルルの運営に際してクラウドファンディングを実施されていましたが、その他資金調達はどのようにおこなわれているのでしょうか?
ケアくらの運営資金は、事業収入が3割、寄付収入が2割、助成金が5割といった割合です。事業収入は、だいかい文庫での飲食の売り上げや、一箱本棚オーナー制度(*2)での収入などが当たりますね。
(*2)だいかい文庫にある棚のオーナーになって、一区画に自分のお気に入りの本やおすすめ本を自由に置ける制度
寄付については、ケアくらの活動を応援してくれている青年会議所(JC)の元保健師さんが、他のJCの方にアポを取って5〜6件の企業にプレゼンする機会を設けてくださいました。そして、そのうちの1つの企業様が支援をしてくださっています。
助成金は、今は民間のものを活用しているので、今後だいかい文庫やテルルで自治体の受託事業がとれると安定して運営できそうだなと思っています。
豊岡市の方や地域外の方が視察にいらっしゃったり、自治体の方の中には一個人としてだいかい文庫に足を運んでくれる方もいらっしゃるので、そのような機会を通して取り組みへの理解を深めていただけたらと思っています。
地方で組織運営をするなかで感じる難しさ
ー資金調達面で、地方ならではの難しさを感じることはありますか?
私たちのスタッフは若手が多く、必ずしも社会経験豊富なわけではないので、営業面などでは難しさを感じることがあります。地方では営業をかけられる先も限られており、なかなか資金的支援を得にくい側面があります。
また、私たちは軸となる事業があってそれをいくつもの地域に同じように展開するのではなく、地域に合わせて必要な事業をそれぞれ立ち上げて運営しているので、その度に初期費用や体制を整えるためのコストがかかる大変さがあります。スタッフも少しずつ増えてはいるのですが、手が回り切らない状況もありますね。
ーそのような課題について、どのように解決の道を探られているのでしょうか?
事業規模が同じくらいか、もう少し大きいくらいの団体さんと相談する機会を持つようにしています。ただ、資金面などの話を聞いているとどこも苦労しているなという印象です。
特にケアくらのように、特定の分野の特定のイシューのみを取り扱うわけではなく、その地域に必要なさまざまな事業を小さく展開し、その地域特有の課題に深くアプローチをしていく事業は、地域外の人から理解を得て寄付や助成金を得ていくことが難しい面があります。
制度を活用できるものもあれば活用できないものもあり、各事業は地域においてとても良い動きなんだけど、お金にはなりづらい。しかも小さい事業がたくさんあるのでマネジメントはとても大変、というような感じですね。
新公益連盟(社会的企業・NPO団体連盟組織として、行政・企業・住民等とともにセクターを越えた「コレクティブ・インパクト」を目指す組織)の集まりでは、地方で水のように活動しているNPOの方との出会いがたくさんあり、そうした方々と関わって話をする機会は大切だなと思っています。
また、特定の地域を対象とした事業であるからこそ、地域の方々の理解・協力・参画がとても重要だと思うので、今後も地域の方々と協働しながら持続可能な事業のあり方を模索していきたいですね。
まとめ
今回は、ケアくら代表理事の守本さんに、ケアくらに関わるスタッフの特徴や事業運営面の現状と難しさ、今後の展望について伺いました。ポイントを以下にまとめます。
- ケアくらでは、保健師をやっていた方やプレイワーカーをやっていた方がいたり、さまざまな専門知識を持つ仲間が働いている。
- リンクワーカーとは、医療機関や行政、地域の民生委員や相談員、NPOなど、フォーマルな機関からインフォーマルな機関まで幅広い地域・社会資源につなげることで、その人を見守るコミュニティを形成する役割を果たす人のこと。
- 社会的処方とは、1980年頃にイギリスで誕生した、薬ではなく人とのつながりを処方することで、社会的孤立を解消していこうという考え方のこと。
- 資金面では、特定の分野の特定のイシューのみを取り扱うわけではなく、地域に必要なさまざまな事業を小さく展開していくので、寄付や助成金の獲得が難しい側面がある。
※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません
この記事は役に立ちましたか?
記事をシェアしてみんなで学ぼう












