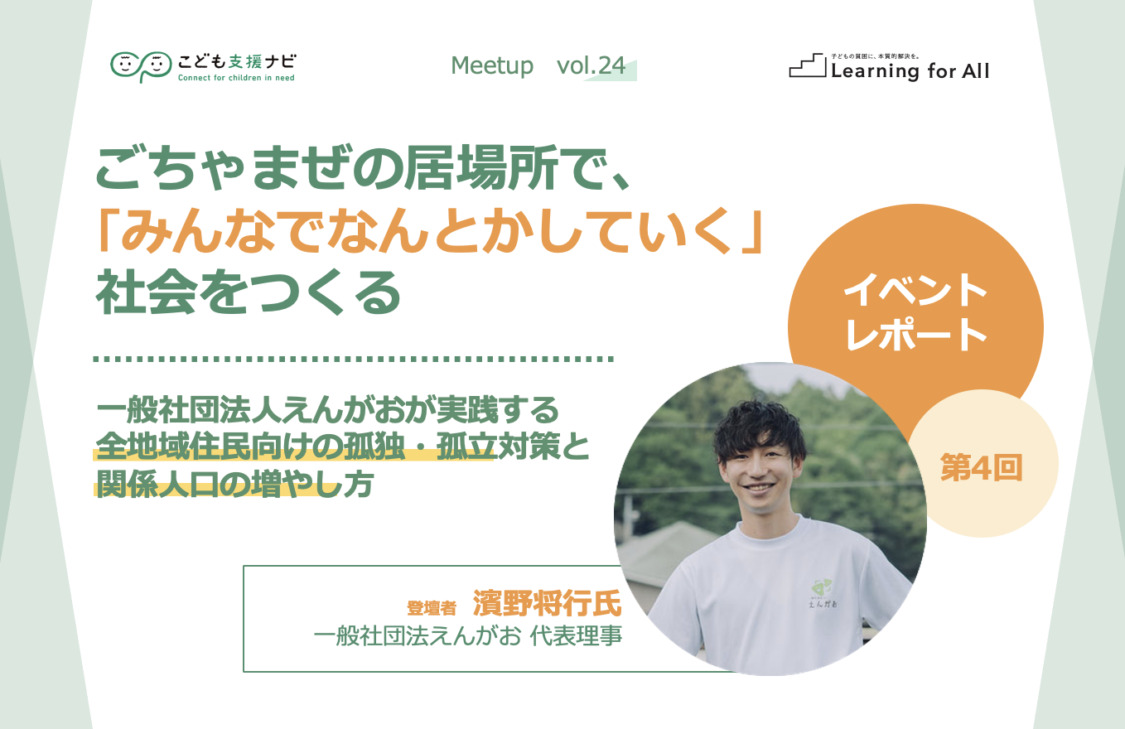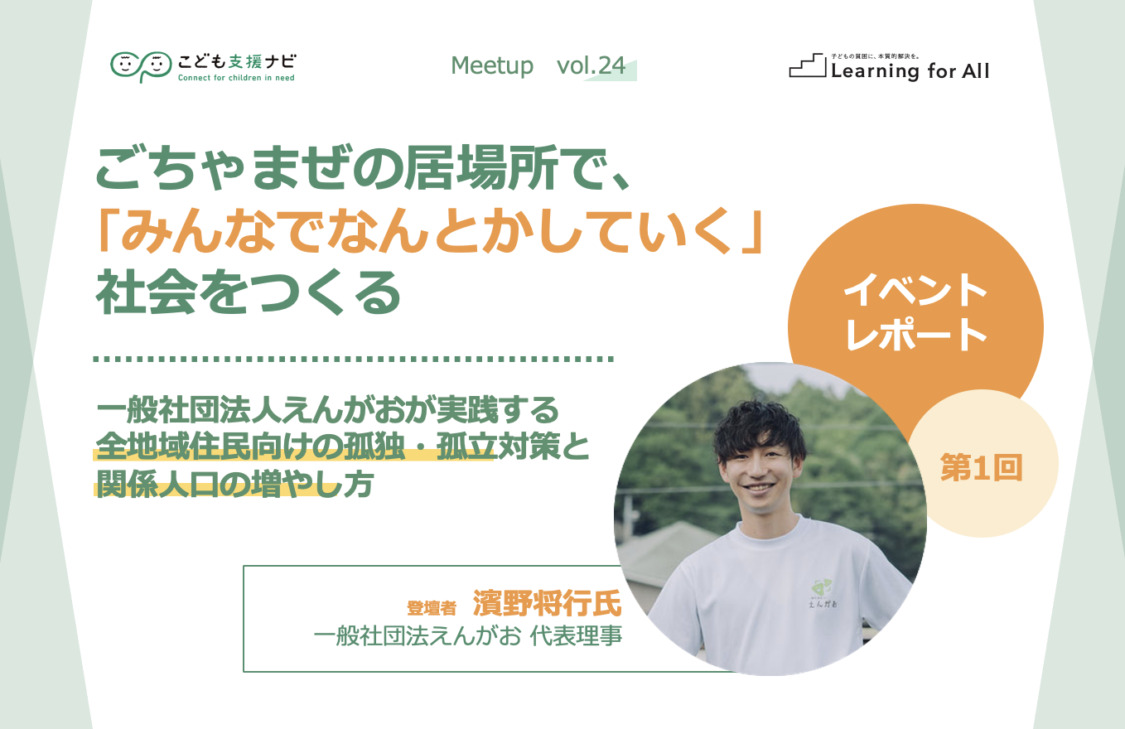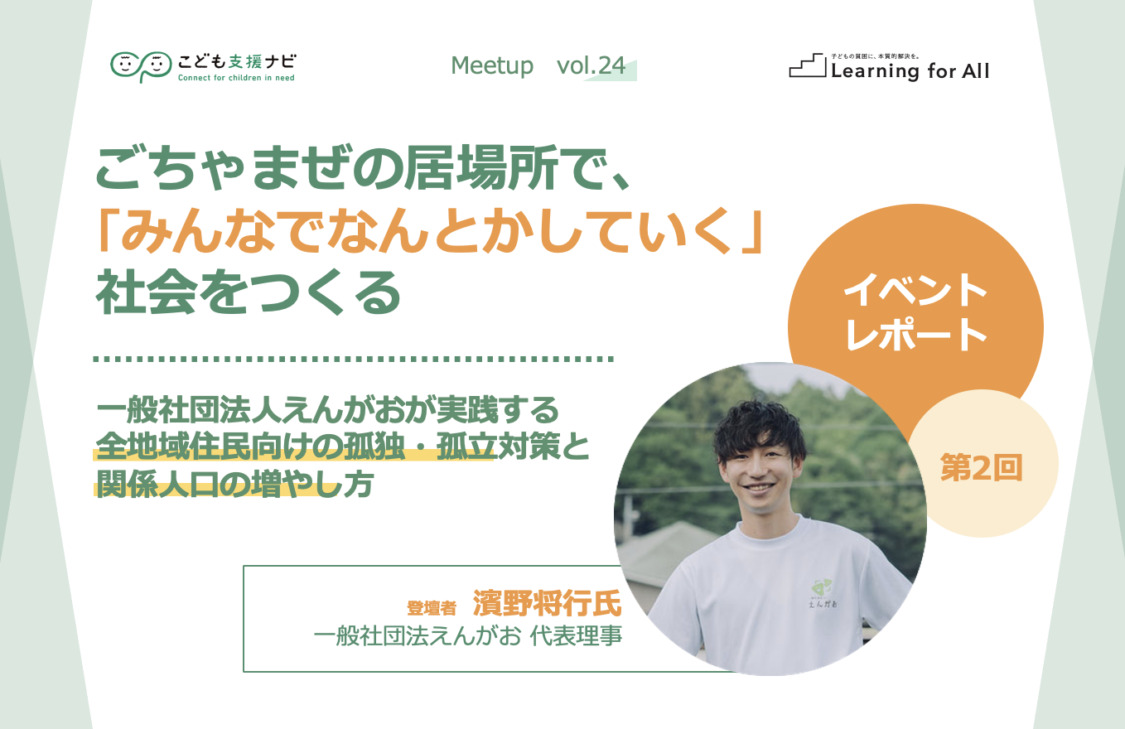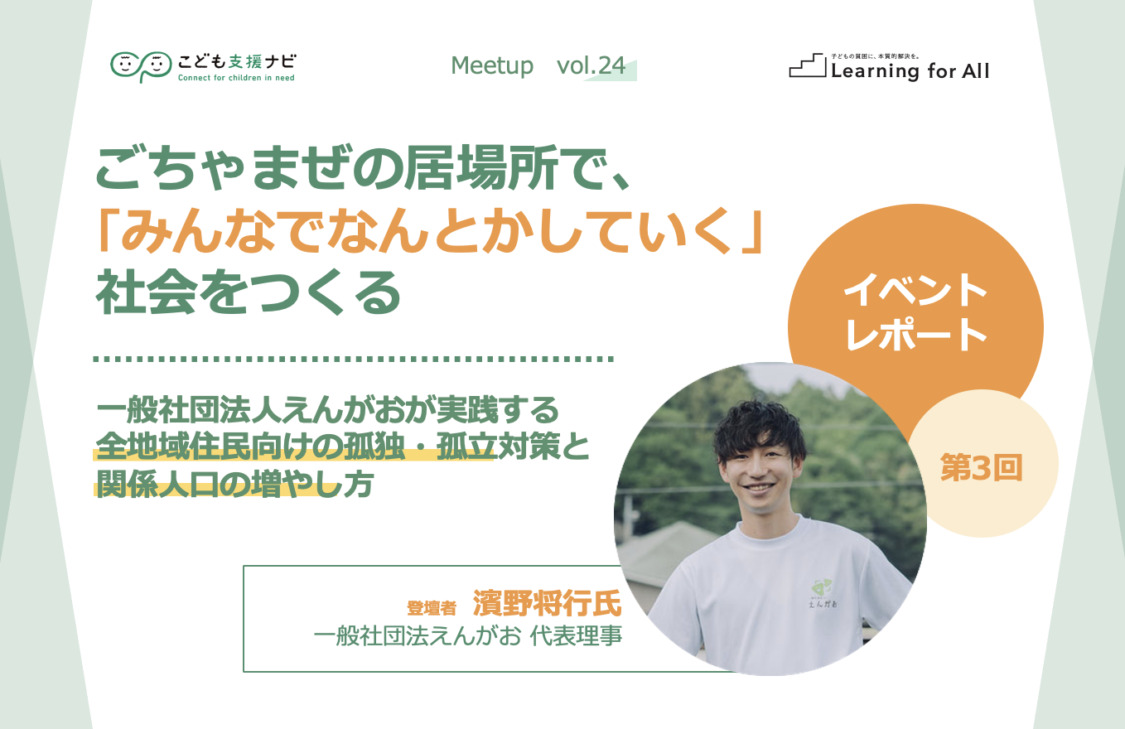2024年11月28日に、子どもに向き合う全国各地の支援者が学び/知見/意見をシェアするオンラインイベント「こども支援ナビMeetup」の第24回が開催されました。
今回は、一般社団法人えんがお(以下、えんがお)の代表理事である濱野 将行氏をお迎えし、「ごちゃまぜの居場所で、『みんなでなんとかしていく』社会をつくる 〜一般社団法人えんがおが実践する全地域住民向けの孤独・孤立対策と関係人口の増やし方〜」というテーマで、えんがおの実践や濱野氏の知見・お考えをお話いただきました。
イベントレポート最終回の第4回では、モデレーターに認定NPO法人Learning for All (以下、LFA)の今村友加里氏を迎えた参加者との質疑応答の様子をお伝えします。
過去の連載はこちら:

プロフィール:濱野 将行 氏
一般社団法人えんがお 代表理事。
栃木県矢板市出身、作業療法士。大学生の頃、東日本大震災を期にNPO活動に関わり始める。大学卒業後、老人保健施設で作業療法士として勤務しながら「学生と地域高齢者のつながる場作り」を仕事と両立する中で、地域の高齢者の孤立という現実に直面。根本的な解決に届く地域の仕組みを作るため、2017年5月「一般社団法人えんがお」を設立し、高齢者と若者をつなげるまちづくりに取り組む。
現在、年間延べ1000人以上の若者を巻き込みながら、徒歩2分圏内に9軒の空き家を活用し、高齢者サロンや学童保育、フリースクール(不登校支援)・地域食堂・シェアハウス・障害者向けグループホームなどを運営。子供から高齢者まで、そして障がいの有無に関わらずすべての人が日常的に関われる「ごちゃまぜの地域づくり」を行っている。
著書に「ごちゃまぜで社会は変えられるー地域づくりとビジネスの話」「居場所づくりから始める、ごちゃまぜで社会課題を解決するための不完全な挑戦の事例集」など。
好きなものはビールとアウトドア。

プロフィール:認定NPO法人Learning for All LFAラボ全国連携チーム マネージャー
今村友加里氏
IT系コンサルティングファーム、教育系BtoBベンチャー等を経験した後、2022年にLearning for Allに入職。全国の子ども支援者に向けた研修・ナレッジ提供や、ネットワークづくりに携わる。子ども支援に関わる方々が日々学び合い、つながり合うことを目指して活動している。古い映画と音楽が好き。
空き家・空き店舗活用の事例について
—参加者)デイサービスで子ども食堂をしていますが、不登校が多くて社会に出ていない若者もいるので、そうした子ども若者向けの居場所を作りたいと思っています。場所がないのが悩みなのですが、空き家はどうやってゲットしましたか?
濱野:えんがおの徒歩圏内にある空き家活用の事例は、都市と地方都市に分けて考えると、あくまで地方都市型だと思ってもらったほうがいいと思います。
まず都会でやるとしたら、今増えてきているビル型がおすすめです。たとえば、2階が子どもたちの居場所で3階が高齢者向けの居場所、4階が障害者向けの居場所、そして1階が誰でも来ていいスペースというパターンが挙げられます。こうすると、施設の収益も得ながら1階でいろいろな人がごちゃまぜになるという付加価値が生まれるので、他施設との競争に勝ちやすいです。
地方都市型は空き家活用がおすすめですが、空き家の見つけ方で言うと、私たちはエリアを決めて地道に散歩して見つけることが多いです。いい感じの空き家を見つけたら、何回か夕方に見に行って空き家かどうか確認して、近所の人に話を聞いたりします。そこから近所の人に空き家の持ち主さんを紹介してもらうこともあります。
また、空き家や空き店舗探しは地域の商工会議所も強いです。こうした居場所は空き家だけでなく空き店舗との相性もいいので、地域の商工会議所と繋がりをつくっていろいろ話を聞いてみるのもいいと思います。
虐待や不登校などの子どもに対するえんがおの関わり方
—参加者)虐待や不登校など心に傷を負ってしまっている子に対して、どのようなことを意識して関わっていらっしゃいますか?
濱野:まず、全員がえんがおのようなごちゃまぜの場にいなくていいと思っています。えんがおのようなオープンな場が合う人もいれば、不登校生向けのフリースクールのようなクローズドな場が合う人もいると思うので、一人ひとりが自分に合う場にいられるような選択肢を増やすことに重点を置きたいですね。
えんがおでは、不登校や中退、家庭の事情で居場所がないなど、いわゆる社会では失敗と捉えられるようなことを、フラットに捉えてオープンに対話する空間づくり(=オープンダイアログ)をしています。
たとえば、えんがおに来ているおばあちゃんは普通に「私認知症だからさ〜」と言ってますね。また、不登校生の間では「出席日数が多いと負け」みたいな文化もあって、不登校の開始時期によって先輩・後輩が決まったりしています(笑)。
しかし、オープンな空間だからといって最初から何でもかんでも話さなければいけないわけではありません。
最近では不登校生向けのアウトリーチをしているのですが、そこから拠点に来てくれるようになった子は、最初人がたくさんいる場所は怖くて、奥の静かなスペースで過ごしていました。そうやって過ごす中でも、えんがおで不登校の子が不登校をネタに明るく話している様子を見て、「そんなに隠さなくていいんだ」「悪いことじゃないんだ」と思ってちょっとずつ話し出してくれています。こうしたオープンダイアログ的な関わりはえんがおではとても大切にしていますね。
地域に選択肢をつくり続けることを重視した取り組み
—参加者)支援や居場所に繋がらなかったり、現状を隠したい家族や当事者もいると思うのですが、支援の必要性があった場合、はじめの一歩はどのようにされていますか?
濱野:支援や居場所に繋がらないというのは、本人や家族が繋がりたがっていないというのがよくあると思います。私も現場で、本人たちが支援を受けようと決断しない限りなかなか物事が前に進んでいかないという場面に遭遇しますが、だからといってその人たちを放っておいていいのかというと、そうでもないですよね。
こうした場合、私たちは「選択肢をつくり続けること」が大切だと思っています。
高齢者の例で言うと、高齢の男性はえんがおにはほぼ来ないんですが、ぶっちゃけ来なくてもいいんですよ。参加者数が必ずしも実績ではなくて、その人を誘い続けること、つまり選択肢をつくり続けることが重要です。
たとえば、おじいちゃんが一人で家でテレビを見て過ごしていたとしても、誰からも誘われずに一人で過ごしているのは「孤立」ですが、えんがおや地域の民生委員から誘いを受けたけど断って一人で過ごしているのは「選択」ですよね。
この「選択」があることで、状況的には同じでも心持ち的には違ってくるはずなんですよ。むしろ「断らせてあげる」ことも重要で、たとえ支援に繋がらなくても、誘われて断ったという事実によって孤立ではなく選択にすることが重要だと思います。人によって頻度は変えますが、月1回でも3ヶ月に1回でも誘い続けてゆるく繋がり続けます。こうしているとどこかのタイミングで「それなら行ってみようかな」となることもあります。
なので、高齢者でも不登校でも子ども支援でも、支援や居場所の参加者数ではなく、地域に選択肢をどれだけ増やしたかが重要だと思っています。個別の状況によって対応は異なると思いますが、基本的にえんがおではこの考え方をベースにして取り組んでいますね。
えんがおの組織基盤について
スタッフは「欲しい!」と思った人を一本釣り
—参加者)えんがおのスタッフさんはどのように集まりましたか?
濱野:スタッフはまだ公募をしていなくて、まず地域の人や学生といった関わってくれる人の数(関係人口)を増やして、関わりの様子を見る中でえんがおに欲しいなと思った人を一本釣りするスタイルでやっています。
これは、公募して新しいスタッフさんにえんがおのカルチャーを説明してマッチングして、そこから教育して、というプロセスで採用するよりも、えんがおのカルチャーがしっかりわかっていて同じような思いを持っている人を採用したほうが採用・教育面のコスト的にえんがおに合っているからです。
関係人口を増やすために、いろいろなイベントをやっていろいろな人に来てもらって、よさそうな人にはこちらから声をかけてバイトで入ってもらって、バイトから常勤・非常勤職員としてメインで働いてもらうことが多いですね。
あとは、人が集まりやすい組織の特徴として、みんな楽しそうに働いているというのがあると思います。従業員が幸せな組織をつくれば、自然とその周りにいい人が集まってスタッフの質も高くなるので、小手先のテクニックではなくてスタッフが幸せな組織をつくれば自然と人は集まってくるという感覚でいます。
相談から職員と繋がり、そこから繋がりを増やしていく
—参加者)行政との関わり方で心がけていることや関わる際のコツなどはありますか?
濱野:行政の方には、「こういうときどうしたらいいですか?」といった相談をよくします。相談ベースだと、結構現場の話を聞いてくれる人が出てきやすいと思っていますね。まずそこで繋がった方と連携して進めていきます。
あとは、子ども課から障害課など複数の課をまたぐケースだと、仲良くなった課の職員さんに「〇〇課にこんな相談をしたいんですが、聞いてくれそうな方いますかね?」と相談して、仲の良い職員さんに別の職員さんを紹介してもらいます。行政の特徴として、他の課からの紹介だと丁寧に扱ってくれるというのはあると思います。
こうした関わり方のコツは、行政でも地域の自治会長でも民生委員でも結局は一緒かなと思いますね。
まとめ
今回は、えんがお 代表理事の濱野さんに、空き家探しのコツやえんがおでのオープンダイアログ的な関わり方、地域に選択肢をつくり続けることなどについて伺いました。ポイントを以下にまとめます。
- 空き家はエリアを決めて地道に散歩して見つけることが多く、空き家や空き店舗探しでは行政だけでなく地域の商工会議所も強い。
- えんがおでは、不登校や中退、居場所がないなど、社会では失敗と捉えられるようなことをオープンにする(=オープンダイアログ)文化をつくっている。
- 支援を断ることも「選択」と捉えて、選択肢をつくり続けること、地域に選択肢をどれだけ増やしたかが重要である。
- スタッフが幸せな会社をつくれば自然と人は集まってくるという感覚で従業員の幸せを追求している。
※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません
この記事は役に立ちましたか?
記事をシェアしてみんなで学ぼう