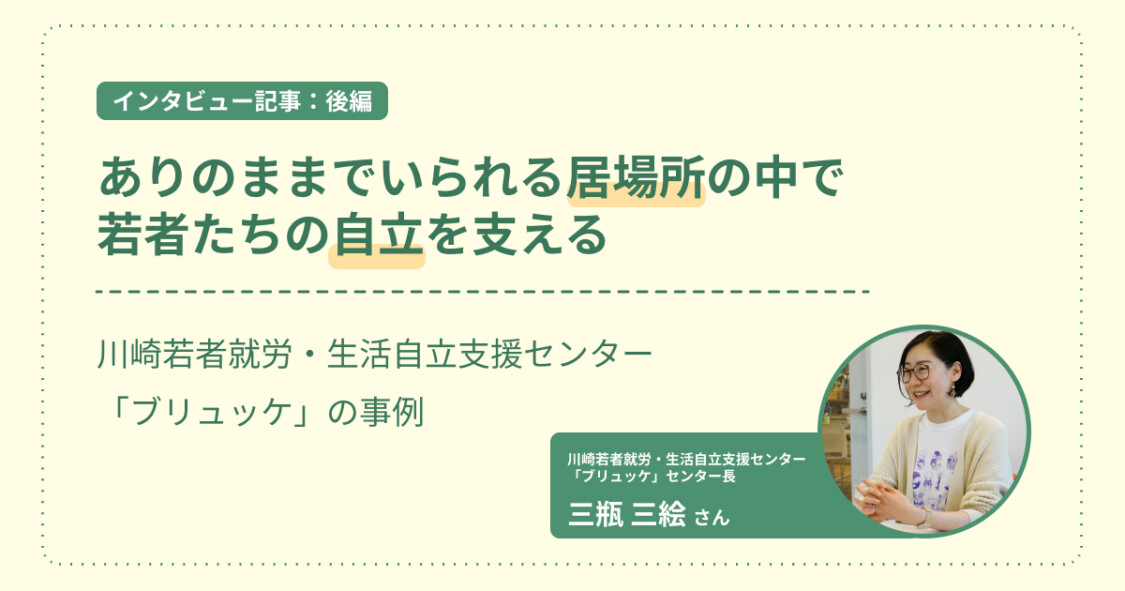日々困難を抱える子どもや若者と接する中で、一般的な家庭で当たり前とされている「愛」や「誰かと一緒に暮らす幸せ」を十分に受け取っていないと感じる場面はありませんか。家族との情緒的な関わりや経済的な援助はとても貴重なもので、それを得られない子どもが多くいると実感している支援者は多いのではないかと思います。
一般社団法人ソーシャルペダゴジーネットが運営する「いとこんち」は、安心・安全な家庭体験の不足を埋めるべく、職員が「親戚のおじさん・おばさん」のような立ち位置で、子どもや若者と関わる居場所です。社会的養護の卒業生やヤングケアラー、ひとり親家庭など、いろいろな背景を持つ子どもや若者が訪れ、「おじさん・おばさん」と一緒に時間を過ごしています。
今回は、北海道札幌市に子ども・若者の居場所「いとこんち」を設立し、地域社会による子育てに取り組んでいる、一般社団法人ソーシャルペダゴジーネット代表理事・松田氏にお話を伺いました。
連載第2回では、いとこんちをどのように広報しているかや、子どもたちと接する際に松田氏が心がけていることを教えていただきます。
連載第1回はこちら:
関連記事はこちら:

プロフィール:松田 考氏
一般社団法人ソーシャルペダゴジーネット代表理事、公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会こども若者支援担当部長。
支援者だけに広報する〜多様な子ども・若者がいとこんちを訪れるまで〜
—いとこんちでは、どのように対象となる子どもや若者に拠点の存在を知らせているのでしょうか。
いとこんちを立ち上げた当初から、一般向けには広報しないと決めていました。なぜなら、本当に必要な人ほど情報は届かないからです。そこで、子どもの身近にいる大人、具体的には学校の先生、保健師、保育園、児童養護施設、自立支援コーディネーター、保護課などにだけ取り組みを伝え、紹介をお願いしました。その際、利用のために満たすべき要件は設けず、年齢・所得・障害の種別などにかかわらず、大人から見て支援が必要だと思った子どもを紹介してもらう仕組みにしました。
例えば、「家庭的な体験が不足している子ども・若者」や「家庭という枠組みから逃れるのに苦労している子ども・若者」が対象なので、その筆頭として社会的養護の子どもたちが紹介されます。社会的養護で育った子どもたちは、18歳を超えると就職や専門学校に通うために北海道各地から札幌に来ます。その生活をサポートするために自立支援コーディネーターという方がいて、病気になったら病院に繋いだり、就職に困っていたらハローワークに繋いだりする役割を担います。
けれども、「深刻に困っているほどではないけど、誰かとお話ししたい」、「電気代の払い方を教えてほしい」など、相談と雑談の合間のようなニーズが多く存在しました。そこで、自立支援コーディネーターの側から「いとこんち」に紹介させてほしい」という要望が多くあり、登録が増えました。

画像:いとこんちのXより
他にも、保育園や保健師から「心配している家庭があるけど、児童相談所に相談したら二度と来てくれなくなる」といった、児童相談所には繋ぐことが難しいご家庭を紹介いただくこともあります。いとこんちに登録された後も、いとこんちだけでどの程度支援するかを判断するのではなく、学校や行政などと連携し、一緒にアセスメントやプランニングを行っています。
—たくさんの専門職や行政職と協働されているのですね。ちなみに、連携する中で大切にしていることはありますか。
なるべくお互いの立場を尊重することだと思います。お互いが得意とすることを確認した上で、それでもまだ解決できていない課題があるから、そのために一緒にできることをしよう、と相手に伝えています。
また、連携の中で限界を感じることがあれば、その人個人に原因を帰着させるのではなく、制度・枠組みによる限界であるとお伝えするように心がけています。
「子どもたちのために」という目標は一致しているので、私はできるだけ多くの方と協力したいと考えています。さまざまな大人の事情はあれど、それを乗り越えて、みんなで連携し合うことができれば嬉しいです。
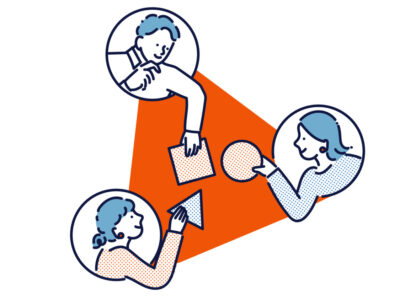
画像:illustAC
子どもの「属性」と「個別性」のバランス〜子どもの特徴を掴むには〜
—さまざまなバックグラウンドを持つ子ども・若者がいとこんちを利用していますが、それぞれの背景によって子どもの特徴はありますか。
正直、パターンがないわけではないと思います。ただ、パターンを見極めつつ、そこに囚われすぎず個別の課題に向き合うというバランスが大事だと思っていて、悩ましいところです。
例えば、社会的養護出身の子どもたちは大人の顔色を窺って発言していることが多いと感じます。具体的には、イベントを企画すると「行きたいです」と言ってくれますが、当日になると休む、といった形です。その理由が育った環境によるものなのか、年齢を重ねて「大人の社交辞令」を身につけているからなのかは、正直判別がつきません。なので、「家庭環境によるものだ」と断定し、私たちが想像する「子どものライフストーリー」のようなものに当てはめすぎないように気をつけています。
まとめ
今回は、松田さんに、いとこんちの取り組みについて伺いました。ポイントを以下にまとめます。
- いとこんちの活動は、関係者にのみ広報していて、関係者が子どもや若者を紹介してくれる。登録に条件はなく、大人から見て支援が必要だと思った子どもや若者が対象となる。
- いとこんちでは、相談と雑談の間のようなニーズを拾いながら、行政や学校と連携している。
- 子どもの背景によって、行動に特徴もあるが、そのパターンに囚われすぎずに、個別に向き合うことも重要である。
連載第3回では、一般社団法人を立ち上げた経緯や今後の展望をお聞きします。
※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません
この記事は役に立ちましたか?
記事をシェアしてみんなで学ぼう