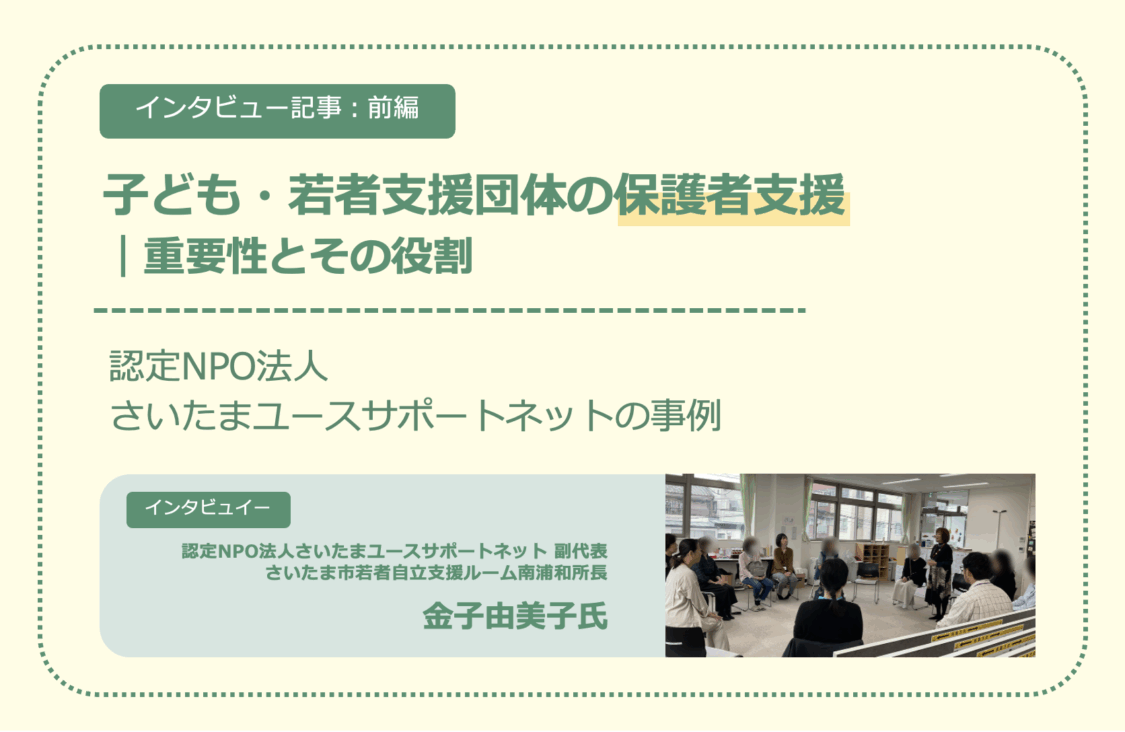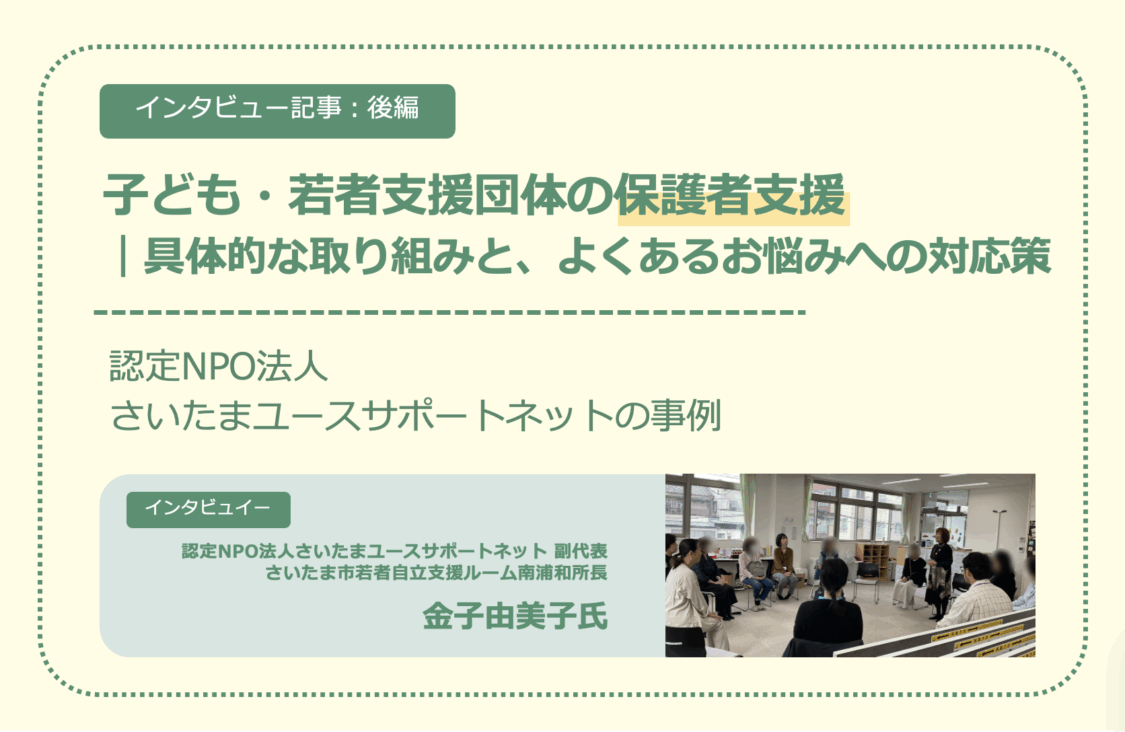地域の居場所や学習支援で子ども・若者を支援していく中で、保護者や家庭自体が複雑な困難を抱えているケースに出会うことも少なくないでしょう。
今回は、認定NPO法人さいたまユースサポートネット(以下、さいたまユースサポートネット)の副代表であり、過去には中学校養護教諭も務められていた金子由美子氏に、さいたまユースサポートネットが行う保護者支援について伺いました。
前編では、なぜ保護者支援を重要視しているのか、保護者や家庭が抱える困難や、子ども・若者の居場所の保護者支援における役割などについて伺います。
関連記事はこちら:

プロフィール:金子由美子氏
一般社団法人“人間と性”教育研究協議会代表幹事、一般社団法人日本思春期学会理事、NPО法人チャイルドライン支援センター理事、子ども支援センターピッピ理事など埼玉県内公立中学校養護教諭を務めた後、子ども・若者自立支援組織の理事を多数務める。さいたまユースには設立当初より理事として携わり、2016年より副代表、現在さいたま市若者自立支援ルーム南浦和所長。
地域の子ども・若者を包括的に支援するさいたまユースサポートネット
—まずは、さいたまユースサポートネットの取り組みの概要を教えてください。
私たちは2011年に活動をスタートし、さいたま市という地域に根差して、貧困をはじめとする様々な困難を抱えた子ども・若者とその家族が安心して相談できる「地域の居場所」であり続けるために活動をしています。
活動のきっかけとなったのは、代表の青砥が出した『ドキュメント高校中退』という本でした。居場所を開始する前から地域の不登校や引きこもりの子どもたち、その保護者と関わりがあったのですが、その本が多くの反響を呼んで、「やはり地域で若者や子どもたちの居場所が必要だよね」という声があがったことが始まりです。
最初は地域の公民館を借りて「たまり場」という場所をつくりました。そこは住んでいる市町村も年齢も関係なく誰でも来ていいよ、という形で、スタッフは大学生のボランティアもいれば地域の方もいて、「誰が支援者で誰が利用者か」という垣根もあまりない場所でした。
そこから少しずつ、勉強を見てほしいとか、相談に乗ってほしいという声が増えてきて、私たちも徐々に支援体制を整えていきました。その活動が評価され、さいたま市が義務教育終了後の若者の居場所として「さいたま市若者自立支援ルーム」という委託事業を開始し、現在市内2ヶ所でさいたまユースサポートネットが委託を受けて運営しています。
それに加えて、生活保護世帯や児童扶養手当を受けている中高生向けの学習支援を、最初は5区くらいから始め、現在では市内全区で実施をしています。加えて進学に特化した学習支援教室や、小学生向けの学習支援も実施しています。
また、特にひとり親家庭の子どもを中心に受け入れている小学生向けの居場所や、最近では「バーチャルユースセンター」といったオンラインの取り組み、ヤングケアラー支援にも力を入れています。
自主運営の取り組みから始めて市の委託事業に繋げたり、助成金申請なども行いながら、本当にさまざまな世代・背景を持つ子どもや若者を地域の中で支える、立体的で包括的な支援を行っている団体になってきていると考えています。
子ども・若者の支援において、保護者のサポートが重要な理由
ーさまざまな子どもたちを支援される中で、なぜさいたまユースサポートネットでは子どもだけでなく保護者もサポートしていくことを重要視されているのでしょうか。
私たちが保護者支援を大切にしている理由は、子どもが抱える困難の多くは、家庭の中や保護者の困りごとと深くつながっていることが多いと考えるからです。
たとえば、たまり場を始めた当初から、不登校や引きこもりのお子さんを保護者が連れてきてくださることがよくあります。でも、お話を聞いていくと保護者自身も長い間悩みを抱えながら、周りから「あなたの育て方が悪い」と言われたりして、誰にも相談ができなくなっていたり、周囲に不信感を抱いていたりします。
そうなると、子どもも親も社会との接点を失ってしまって、ますます孤立していきます。特に経済的に厳しい状況にあったり、ひとり親で働き詰めだったりすると、子どもの発達に課題があっても病院に連れて行く余裕がなく、専門家の見立てを受けられずに自分の育て方のせいだと追い詰められてしまう。そういうケースも本当に多いです。
だからこそ、保護者が信頼できる相手とつながって、子どもを安心して任せられる場所・自分の悩みを安心して話せるようになる場所が必要だと考えています。子どもが居場所に通うようになって元気を取り戻していくと、それを見てお母さんの表情もパッと明るくなるんです。「うちの子、こんな話をしてくれるようになったんですよ」と嬉しそうに話したり、私たちとも前向きな気持ちで接してくださるようになったりします。私は、子どもが変わることで保護者も変わるし、その逆もまたしかりだと思っています。
ーどのような状況・困難を抱えていらっしゃるご家庭が多いと感じられますか。
本当にいろいろなケースがありますが、やはり一つの困りごとというよりは、複数の困難が重なっている家庭がとても多いと感じています。
たとえば、ひとり親の家庭だったり、生活保護を受けていたり、経済的に困窮していて日々の生活を回すだけで精一杯という方が多くいらっしゃいます。子どもに何かあって、保護者が放課後3時に学校に呼び出されたりすると、仕事を休まなくてはなりません。非正規雇用の場合はその分の賃金がカットされてしまうので、行くに行けません。そうすると学校からは「おうちでなんとかしてください」と言われてしまったり、保護者自身も責められるのが辛くて学校からの電話を着信拒否したりして、結果、学校という最も身近な相談先も失ってしまうというケースもあります。
あとは、DVの被害を受けている保護者も少なくありません。「子どもが学校に行きたくない」と言う背景に、実は「自分が家にいない間にお母さんがお父さんに暴力を振るわれるんじゃないかと心配で、家を離れられない」といった理由が隠れていることもあります。高齢の両親、精神疾患を抱える家族の中で、自分が家事など生活全般の要を担っているから学校に行けない、というようなケースもあります。
一見すると「子どもが不登校で困っている家庭」として見えるのですが、実はその背景にはいくつもの家庭内の困りごとが重なっている、ということが少なくないですね。

利用者プログラム「家族との関係について」の様子(提供:さいたまユースサポートネット)
子ども・若者の居場所の、保護者支援における役割
ーその中で、保護者支援における子ども・若者の居場所の役割はなんだと思いますか。
子ども・保護者双方にとって、学校以外で定期的に接点を持ち続ける身近な場所になること、安心して話ができる場所であることだと思います。
子どもは学校に行かなくなると、「学校に行っているはずの時間」に外に出ることに後ろめたさを感じたり、朝決まった時間に起きないので夜眠れなかったりして、昼夜逆転の生活になることが多いです。そうすると、保護者とも生活サイクルがあわず、学校に行っていないので話すこともなく、親子の会話が少なくなっていきます。
子どもが居場所に定期的に通えるようになってくると、生活サイクルが整ったり、居場所で起きたことを保護者に話すようになったりします。それ自体が親子関係、ひいては保護者の心の健康につながっていきます。
そうして保護者自身の心が回復してくると、私たちとも前向きにコミュニケーションをしてくださるようになったり、学校とももう一度きちんと話をしてみよう、という気持ちが芽生えてきたりします。ですので、私たちのような第三の場所が学校や自治体との中間のクッションのような存在になることが、すごく大切だと感じています。
保護者支援において大切にしている視点
ー保護者をサポートしていく中で、大切にしている視点を教えてください。
保護者の方はすでにたくさん傷ついて疲弊しています。だからこそ、保護者の過去や現在を正そうとする指導的な関わりではなく、保護者自身の回復もサポートしながら、一緒に子どもを育てていく「子育ての伴走者」という意識で関わるようにしていますね。
例えば経済的に困窮しているご家庭だと、保護者の方も本当は子どもにいろんな楽しい経験をさせてあげたいのに、それができない自分を責めていたりします。自分自身も貧困家庭で育っていて、子どもに何をしてあげたらいいのかわからないという方もいらっしゃいます。
だからこそ、子どもたちに様々な体験の機会を提供したり、保護者がやってあげたくてもできないことを一緒にやっていく存在である意識が大切だと思います。
まとめ
今回は金子さんに、なぜ保護者支援を重要視しているのか、保護者や家庭が抱える困難や、子ども・若者の居場所の保護者支援における役割などについて伺いました。ポイントを以下にまとめます。
- 子どもが抱える困難の多くは、家庭の中や保護者の困りごとと深くつながっていることが多い
- 一見すると一つの困りごとを抱えている家庭に見えても、その背景には複数の家庭の困難が重なっている
- 保護者支援における地域の居場所の役割は、子ども・保護者双方にとって、学校以外で定期的に接点を持ち続ける身近な場所になること、安心して話ができる場所であること
- 保護者自身の回復もサポートしながら、一緒に子どもを育てていく「子育ての伴走者」という意識が大切
後編では、実際の保護者支援の取り組みや、「関わりを拒否する保護者にどう対応する?」など、保護者支援でよくある拠点側のお悩みについて、具体的な対応をお伺いします。
※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません
この記事は役に立ちましたか?
記事をシェアしてみんなで学ぼう