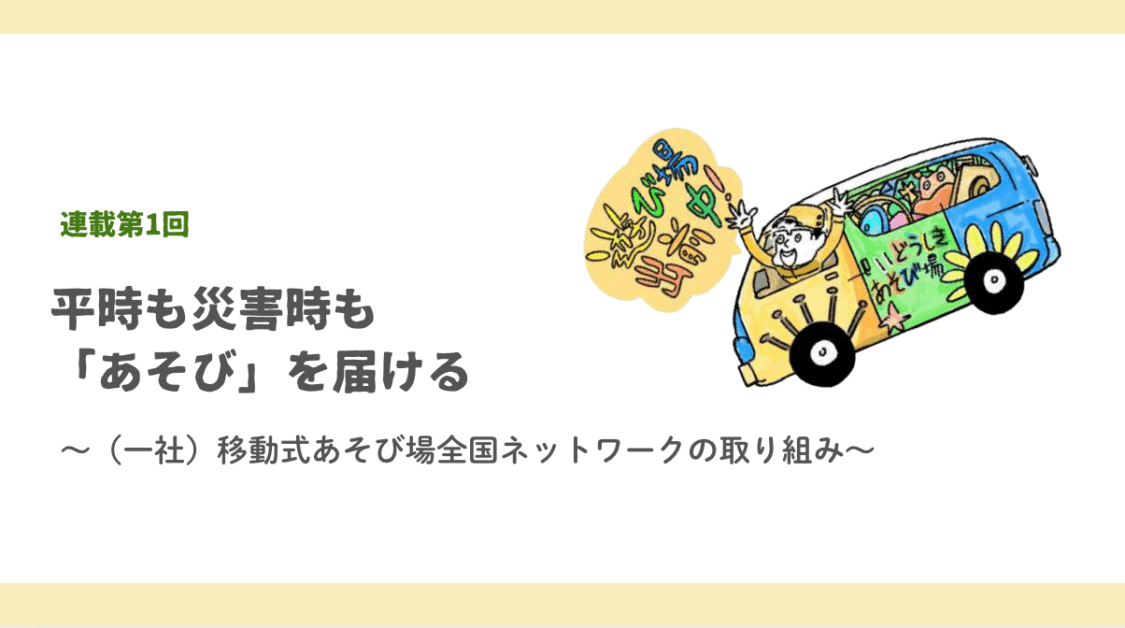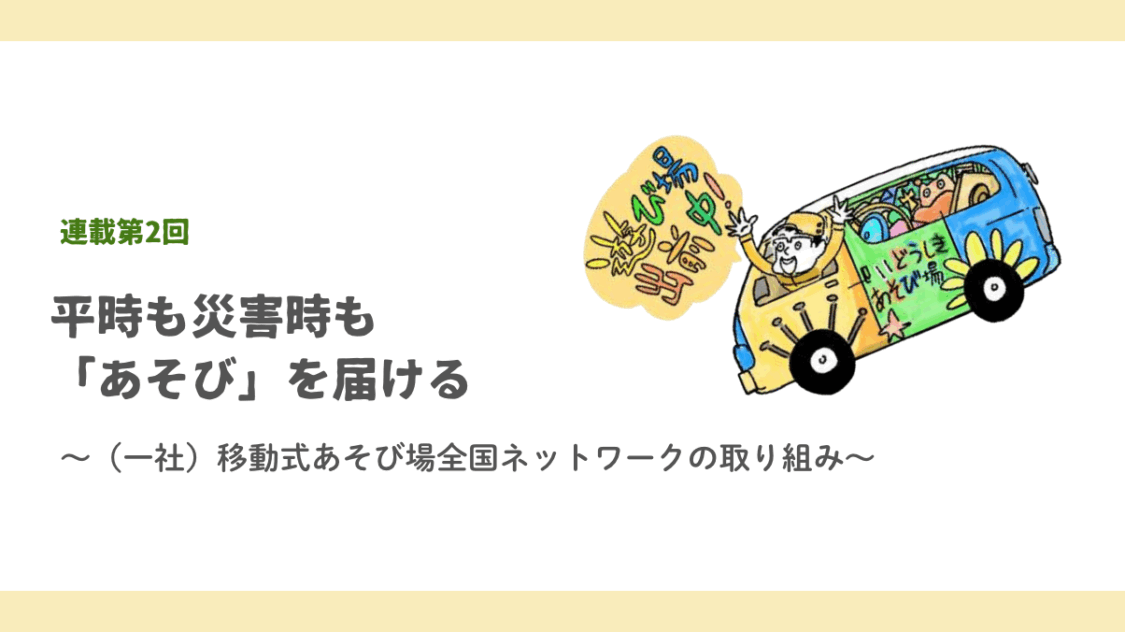近年、大きな災害が増えたり猛暑が続いたりと、子どもたちが自由に外で遊ぶのが難しい状況が続いています。とりわけ、安心して過ごせる「あそび場」が少ない地域では、体験格差や子どもの居場所の喪失が深刻な課題となっています。
そんななか注目を集めているのが、あそび道具を載せた車=プレイカーで全国を巡り、子どもたちに多様なあそびを届ける「移動式あそび場」という取り組みです。現在全国では25~30台が稼働し、これまでに私は全国で延べ42万人以上の子どもたちと出会ってきました。
この活動を創設し、「あそびを待つのではなく、自ら届ける」ことを25年間続けてきたのが、一般社団法人移動式あそび場ネットワークの代表理事であり、プレイワーカーの星野諭さんです。
本連載の第1回では、移動式あそび場が生まれた背景や社会的な意義、そして子ども支援者が現場で実践に生かせるヒントについてお話しいただきます。
関連記事はこちら:

プロフィール:星野 諭 氏
プレイワーカー/一級建築士/こども環境コーディネーター。1978年新潟生まれの野生児。高校から子どものボランティア活動を行い、2001年の大学時代にNPO団体設立。子どもの居場所づくりや地域イベント、環境共生デザインやキャンプ、廃材あそび場やフリースクールなどを実施中。2008年に移動式あそび場を創造し、大都市部や里山、被災地など全国で活動を展開している。
常設拠点の限界から生まれた「逆転の発想」

出典:アウトドアアワード
—移動式あそび場を始めたきっかけを教えてください。
実は最初から移動式を考えていたわけではありません。2001年に学生15名で活動を始めたときは、「もっと自由に遊べる場所を、子どもたちのそばに作りたい」という思いから、東京・神田で常設の拠点を運営していました。しかし2005年、拠点が取り壊され、新しい場所を探しましたが家賃も高く、子どもたちが自由に遊べる場所を見つけることは難しかったのです。
そんなときに街で見かけたのが、自動販売機の補充車でした。車をガチャガチャと開き、中からペットボトルや缶が出てくる。それを見た瞬間に雷が落ちたように「これがあそび道具だったらどうだろう」とひらめきました。
そこから、「来てください」という姿勢を「こちらから出向く」に変えました。都市には空き地や公開空地、道路など、まだまだ活用されていない場所がたくさんあります。そこにプレイカーが出向くことで、あそび場づくりと共に、老若男女が一緒になって遊んで繋がり地域のコミュニティが再構築できるのではないかと考えました。
実際、道路で遊んでいると、子育て世代以外のおじいちゃんおばあちゃんも自然に参加してくれます。公園や施設で「来てください」と呼びかけても関心のある人しか来ませんが、こちらから日常の場に出向くことで、たまたま通りかかった人たちとの出会いや繋がりが生まれるのです。
移動式あそび場が向き合う5つの課題
—なぜ今、移動式あそび場が必要とされているのでしょうか?
移動式あそび場には、以下のような社会課題に応える力があります。
- あそび場の減少:子どもが自由に遊べる場所が少ない
- 社会的孤立:子育ての孤立感や地域の繋がりの希薄化
- デジタル化の影響:子ども同士の直接的な交流が減少
- 運動不足:コロナ禍でさらに深刻化
- 体験やアクセスの格差:距離や経済的理由で参加できない子どもたちがいる
特に5つ目の「体験・アクセス格差」は大きな課題です。素晴らしいあそび場や体験を提供する団体があっても、距離や経済的事情で参加できない子どもがいます。移動式なら、その地域に直接届けることができます。
—子ども支援の現場でも、「来られる子」と「来られない子」の差は大きな問題ですね。
そうです。来られる子と来られない子の差は本当に大きな課題です。移動式にすることで「来られない子」にこちらからあそびを届けることができます。そして、私たちは子どもや親からお金をもらわず、企業や自治体など第三者の支援を受ける仕組みを作り、経済的な障壁を取り除いています。
車自体が遊具になる「プレイカー」の魅力

画像提供:移動式あそび場全国ネットワーク
—プレイカーにはどのような特徴があるのでしょうか?
私のプレイカーは、車自体が遊具に変身することが特徴です。中には段ボール、酒樽、竹、木の角材、大人の楽器など、地域で集めた自然素材が詰まっています。プラスチック製品はほとんど使っていません。
車の上が滑り台になったり、ターザンロープを取り付けたり、夏にはウォータースライダーになるなど、多様な形に変身します。滑り台タイプは全国に2台、他にも車の中にクーラーが入って赤ちゃんが休める子育て支援タイプなど、用途に応じてさまざまなタイプがあります。
—素材あそびを重視されているのはなぜですか?
シンプルな素材は、子どもの想像力を最大限に引き出すからです。木の角材を並べるだけで「ドンジャンケンポン」(角材の上で向かい合った子ども同士が出会い頭にじゃんけんをし、負けた方が降り、勝った方が進んでいくあそび)をしたり、高く積んで遊んだりと、あそび方は無限に広がります。
さらに、活発に動くだけでなく「ぼーっとする」「おしゃべりする」といった、何もしない時間も大切にしています。こうした時間が保証されると、子どもにとっては安心できる居場所になるからです。
子ども支援の現場に生かせる「届ける」取り組み

画像提供:移動式あそび場全国ネットワーク
—大きなプレイカーがなくても、あそびを「届ける」活動はできるのでしょうか?
もちろんです。移動式あそび場は大型車だけではありません。軽自動車にあそび道具を積む小規模なものもありますし、ベビーカーを改造したり、自転車でリアカーを引っ張ったり、さまざまな方法があります。
重要なのは「物をシェアする」という意識です。公園の砂場でも、物の貸し借りでトラブルが起きがちですが、「これはみんなで使うもの」という気持ちがあれば、子ども同士の繋がりが広がります。
—プレイカーより重要なのは「人」だと伺いました。
はい。もっとも重要なのは、子どもに寄り添う「プレイワーカー」と呼ばれる人たちです。プレイワーカーは、子どもの「やりたいこと」を最優先にし、「あれしなさい、これしなさい」といった指示や誘導は行いません。大人が主導すると、あそびでなく教育になってしまいます。
プレイワーカーには、遊ぶための環境を整え、コミュニケーションをコーディネートしながら、見守り支える役割が求められます。
—「届ける」取り組みを始めるために、最初にできることは何でしょうか?
まずは地域に「使われていない場所」がどこにあるかを探してみてください。空き地、駐車場、商店街の一角など、活用できる場所は意外と多いものです。
次に地域の資源を見つけること。酒屋さんに酒樽をもらったり、段ボールを集めたりと、ゴミとして捨てられてた身近な素材が「あそび場の資源」になります。
何より大切なのは、場所に合わせて空間を作ること。芝生でやるケースと駐車場でやるケース、道路でやるケースはそれぞれ全然違います。環境に合わせて空間をデザインする柔軟さが大切です。
まとめ
今回は、星野さんに移動式あそび場が生まれた背景と基本的な考え方について伺いました。ポイントを以下にまとめます。
- 「来てください」から「届けます」への発想転換が、アクセス格差を解決するヒントになる。
- 移動式あそび場は車だけでなく、ベビーカーや自転車など小規模からでも始められる。
- 物より人が大切。プレイワーカーの関わり方が成功の鍵。
- 子どもの「やりたいこと」を最優先にし、大人は見守る。
- 地域の資源と未活用の場所を生かし、その場に合わせた柔軟なあそび場づくりが重要。
第2回では、被災地での活動を通じて見えてきた「あそびの力」と、地域主体の支援のあり方についてお話しいただきます。
※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません
この記事は役に立ちましたか?
記事をシェアしてみんなで学ぼう