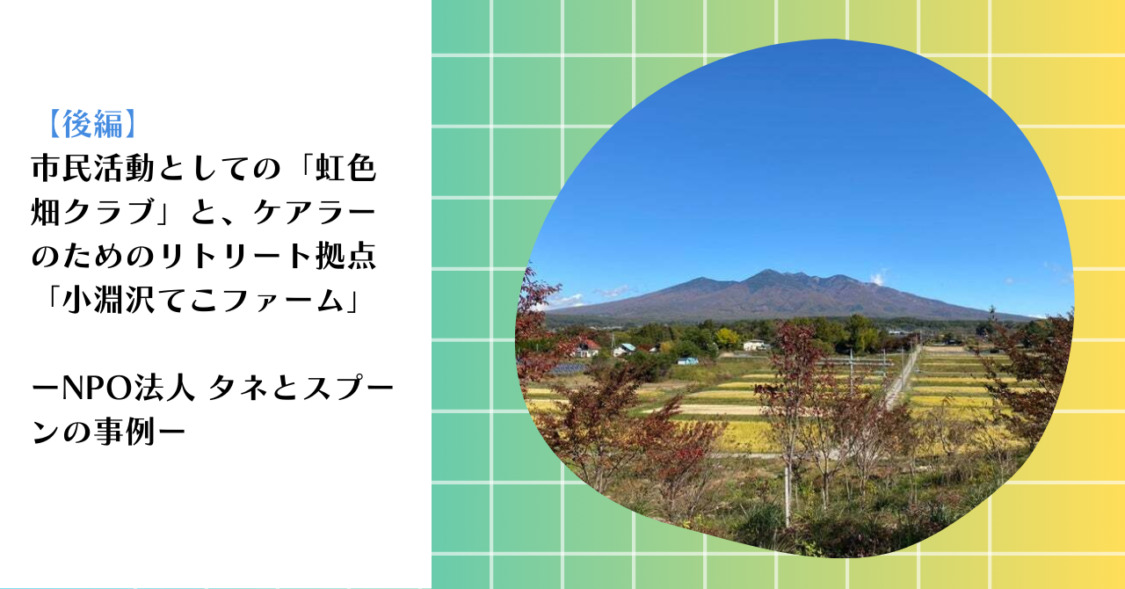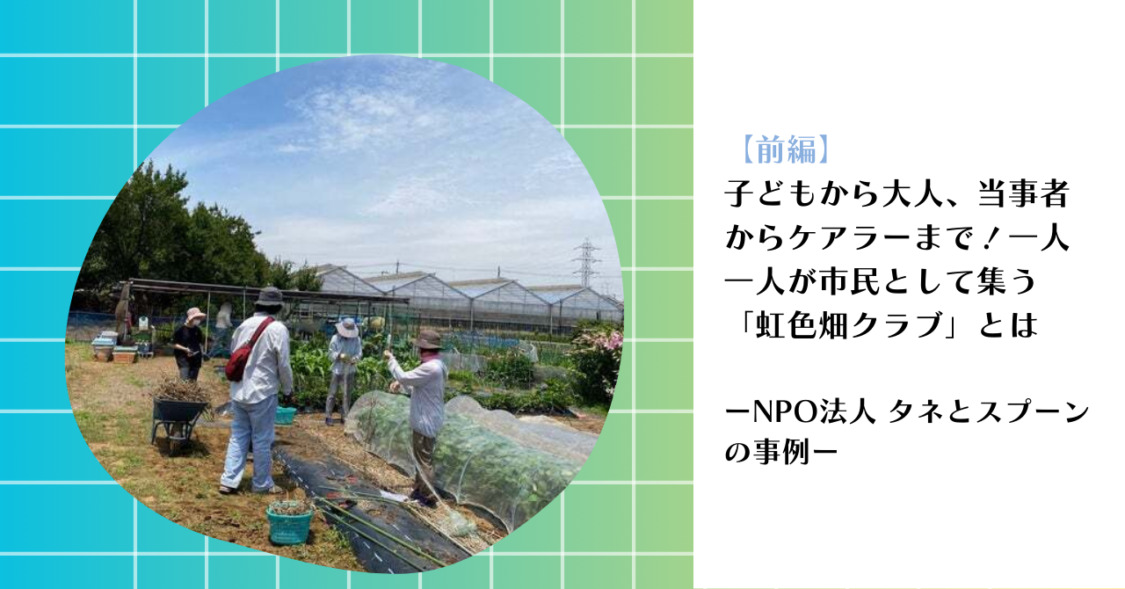前編では、NPO法人タネとスプーン(以下、タネとスプーン)の理事長原田朋子氏に、幅広い年齢・属性の人々が1市民として参加する「虹色畑クラブ」についてお伺いしました。
後編では、虹色畑クラブを「支援」ではなく「市民活動」という形で実施されている理由、またケアラーケアのための場所である「小淵沢てこファーム」について、立ち上げ経緯や活動内容、ケアラーの抱える難しさなどについてお話しいただきます。
前編はこちら:
関連記事:

プロフィール:原田 朋子氏
NPO法人 タネとスプーン 理事長
虹色畑クラブ・小淵沢てこファーム 代表
社会人になってから、企業の仕事についていけないなどの生きづらさを感じ、うつ、発達障害のグレーゾーンなどの診断が出て、一時期引きこもる。その後「成人発達障害と歩む会シャイニング」と出会い、その代表職を経て、2016年に援農活動サークルをスタート。養育里親の活動も行う。
市民活動としての虹色畑クラブ
—虹色畑クラブの取り組みは、生きづらさを抱える子どもから大人までを対象としながらも、支援者から被支援者に対する「支援」という形ではなく、市民が集い、共に活動をしていく「市民活動」の形を取っているかと思います。原田さんが「支援」ではない形でこの場を運営したいと考えられた理由を教えてください。
これは、実際に自分が支援の現場でケアラーとして活動して、「『支援』という括りだけでできることは限られている」と感じたためです。
私が以前働いていた支援現場は若者の自立を目指す団体でした。「自立」とは、いわゆる就労支援のことです。支援する・一般就職を促すといっても、自立の準備ができていない場合や、こういった人達の居場所がそもそも社会にない中で、今の場所から押し出すような、本人の自己決定の尊重が十分にできない支援をしなければならないジレンマがありました。
また、就労継続支援のA型作業所やB型作業所は、決められた日時にきちんと出勤しなければならないため、出勤できるまでに疲弊してまた入院となり、居場所がなくなる方もいました。
こうした状況を見て、行政や支援機関と病院、自宅の間にある第3の居場所が必要だと思ったのです。私自身、支援する立場に疲れてしまったのもあり、「支援する側・される側ではなく、立場や役職といったしがらみのない同じ目線で取り組める仲間になりたい」「支援する場ではなく、今ある福祉の枠組みにはまらない当事者さんの居場所にしたい」と考えていました。
虹色畑クラブでは、農「業」はやっていないので、成果を出す必要はありません。来られなくなる期間があっても問題ないので、自宅療養から就職までの間の回復の場として使うことができます。
1年に1回くらいしか来ない人もいますが、それでも定期的に足を運んでくれるんです。その方には「畑にさえ行けば虹色さんはやっている。いつでも行っていい場所だから、ちょっと良くなったら行こうと思えることが支えでした」と言っていただきました。なので、虹色畑クラブはいつでもやっている、いつまでもあり続けるということが大事だなと思っています。
支援の場ではなく市民活動として行う虹色畑クラブだからこそ、いわゆる支援を謳う場には入っていけない人でも支援に繋がりやすく、また市民活動からスタートできるからこそ見えるニーズや当事者が存在すると思っています。
虹色畑クラブの資金調達について
—虹色畑クラブの運営を続けるために資金調達も非常に大切だと思うのですが、現在どのように運営されているか教えてください。
現在は、横浜市港北区の「地域のチカラ応援事業」からいただいている補助金や民間の財団からの助成金、サポートメンバーの方々がくださる寄付金などで運営しています。毎年いろいろな助成金申請を一生懸命行っていますね。
また、市民農園や家庭菜園をしている畑仲間から種や苗をいただくことも多いです。種や苗は買うと結構高いので、それらを畑仲間がくれるおかげで虹色畑クラブは意外と少ない資金でも運営することができています。
ケアラーケアの場、小淵沢(こぶちざわ)てこファーム

小淵沢てこファーム付近の様子(提供:NPO法人タネとスプーン)
—虹色畑クラブにもケアラーや当事者の保護者が自分自身もリフレッシュする目的で参加されている、というお話しがありましたが、次はケアラーケアの場である小淵沢てこファームについてお聞きします。ここでは、具体的にどのような活動をされているのでしょうか。
トレッキングしたり自然体験、農作業をしたりして、普段は人のために奔走しているケアラーたちがそれぞれ自由に過ごし、気持ちをリフレッシュしています。宿泊イベントのため、夜は参加者同士で自然にいろいろな話をする流れになり、それぞれの思いを吐き出したり共有したりして過ごします。
ケアラーケアの拠点を始めたきっかけ
—小淵沢てこファームでのケアラーケア事業を始めたきっかけはなんだったのでしょうか?
最初のきっかけは、虹色畑クラブに参加しているケアラーの方が最近トレッキングを始めた、という何気ない会話からでした。だったら、私の祖父母が遺した山梨の空き家を拠点にして一緒に登りましょうという話になり、毎月山梨に行くようになりました。
そこで山登りをしたり山梨の家で一緒に寝泊まりしたりして、お互いの現場できついことを吐き出していたら「ここだったら普段は話せないことでも、なんでも話せるな」という思いが芽生えました。場所を変える「転地療法」という感じです。
また、私が社会福祉士の勉強をしていたときの仲間ともこの家で集まりました。そうすると、それぞれの現場の話がどんどん出て、夜通し話すぐらいの勢いで話し続けていました。
私たちは普段守秘義務や個人情報の扱いにシビアな業界にいるので、思っていることをわっと吐き出せる場があまりないんですよね。そのため、地元から離れた山梨の家で、もちろん個人が特定されない形で、みんなで日頃の思いを話し、「こんな話ここでしかできない気がする」と口々に言っていました。
最初はケアラーケアのための場所だけでなく、当事者さんも来られる場所にしようかとも考えていたのですが、それだとケアラーが少し負担に感じてしまう側面もあるねという話になりました。なので、一旦はこの場所は私たちが当事者さんたちのことを考えるのは一切やめて、個人として楽しみリフレッシュする場にしようということになりました。これが3年ほど前のことです。
当時は、私の知り合いの支援者も精神を病んだりしてどんどん辞めていて、そうすると当事者さんも自分の担当がどんどん変わるから落ち着かないんですよね。この悪循環は良くないと思い、ケアラーがリフレッシュできる場、普段溜め込んだ思いを吐き出せる場を作りたいと思ったのがきっかけです。
対当事者だけではない、ケアラーが抱える難しさ
—原田さんから見たケアラーの大変さを言語化するとどのようなものでしょうか?
当事者のことをひたすら考え続けなければならない、相手をなんとかしなくちゃいけない、という姿勢が疲弊に繋がりやすいというのはもちろんあります。
さらに、向き合っている当事者さんの抱える困難を考えることはその周りの家族などについて考えることにも繋がります。なぜなら、当事者さんの困難はその人だけの問題ではなく、家族の問題であることも大いにあるからです。
例えば、当事者の保護者が虐待・DVをしていてそれを目にしていたり、保護者に対して萎縮していたりするケースがあります。また、いじめがあったのにそれを見過ごされたことで心の病に繋がっているケースもあります。このように、個人だけではないさまざまな背景についても考えなければならない大変さがあります。
重たい話を聞く機会も多いですし、やってもやってもなかなか成果が現れない大変さや、頑張ったけれども残念な結果になってしまったという徒労感もあります。
そして、長期引きこもりのケースや家族の根深い問題への支援は成果が出しにくい仕事なのに「成果が出ないのは自分の能力不足なのではないか」と自分を責め始めるんですよね。こうなってしまってバーンアウトするケースが多いです。
さらに、職場の人間関係で疲弊するケースもよくあります。同じ支援者でも支援への異なる考え方を持っていたりするので、それぞれの意見がぶつかり、自分の考えを理解してもらえなかったり否定されたりして疲弊してしまうのです。最近では福祉支援に対する考え方も昔と大きく変わってきているので、昔のままの考えをもつベテラン職員と新しい感覚をもった若い職員の間で揉めることもあると聞いています。
子どもや若者の支援にはいくらでも心を砕けるけども、福祉現場の人間関係で辛くなってしまうケースが多いかもしれないですね。
ー当事者の持続的な支援のためにも、ケアラーのケアや対話の場を充実させることは急務であると感じました。小淵沢てこファームについても、助成金などを得て活動されているのでしょうか?
正直、小淵沢てこファームの運営のための資金調達は苦戦しています。というのも、該当する助成金がほとんどないのです。
助成金は障害者・子ども・高齢者向けの事業には手厚いのですが、ケアラーケアが該当する助成金はほとんどありません。当事者支援を持続可能にしていくためにも、ケアラーたちの心のケアの重要性がより認知されていく必要があると感じています。

小淵沢てこファームでの朝食の様子(提供:NPO法人タネとスプーン)
今後の事業の展望
—最後に、虹色畑クラブと小淵沢てこファーム、それぞれの事業の今後の展望を教えてください。
実は、虹色畑クラブは支援の場ではないと言いながらも、参加者さんから「今まで行っていた支援機関でうまくいかなかった」「相談先がない」などいろいろな相談を受けることが多いので、制度申請や支援者の紹介、自立して生活するまでの身の回りの世話などをボランティアで行っていました。
ただやっぱり、これまで仕事としてやってきた内容をボランティアでやるということでは、やはり継続は厳しいと感じています。虹色畑クラブだからこそ相談できるという利用者さんもいらっしゃることを考えると、今後は報酬をしっかり受け取れるように相談支援の要素も事業に取り入れていかないといけないかなと考えています。
これまでの福祉支援の枠組みと異なる居場所、支援ではない場所ではあるけれど、伴走が必要な人はやはりいるので、自立サポートというような事業は取り入れて、そのための資金調達もしていこうと思っています。
小淵沢てこファームについては、当事者支援を行う別の団体さんに小淵沢てこファームへ来てもらって自然体験などをしてもらうイベントを企画したいなと思っています。他の団体さんの受け入れをすることで当事者さんと支援者さんが一緒に来てくれるので、こちらも来てくれる当事者さん全員の対応をする必要もなく、受け入れやすいかなと思っています。
そうした他団体の受け入れを通して当事者さんに配慮すべきことがわかってくれば、虹色畑クラブやカドベヤの参加者さんの受け入れもだんだんできるようになるかなと考えているところです。
もう一つ考えているのは、里親子の受け入れです。里親だと、他の家庭と違って親子で顔が似ていなかったり年齢がずいぶん離れていたりして、学校などの友だちと同じような親子関係・ママ友パパ友関係を築くのが難しい場合があります。また、子どもがこの先、元の家庭に戻ることを考慮して、周囲に里親であることを明かしていないこともあります。
そうすると、周囲の人たちには自分の思いや悩みを相談しづらく、抱え込んでいる場合が多いんですね。私自身が養育里親(※児童相談所等で保護された児童の一時保護や養育)をしていることもあって、里親とその子どもが気軽に来られる場所にもしていきたいと思っています。
まとめ
今回は、NPO法人タネとスプーン理事長の原田さんに、小淵沢てこファームを立ち上げたきっかけや活動内容、虹色畑クラブと小淵沢てこファームの今後の展望について伺いました。ポイントを以下にまとめます。
- 支援の場ではなく市民活動として行う虹色畑クラブだからこそ、いわゆる支援を謳う場には入っていけない人でも支援に繋がりやすく、また市民活動からスタートできるからこそ見えてくるニーズや当事者が存在する。
- ケアラーケアの拠点は、支援者が疲弊し、当事者も担当者がどんどん変わって落ち着かないという悪循環の改善が必要と感じ事業を立ち上げた。
- ケアラーは、頑張っても成果が出しにくいことによる徒労感や当事者・当事者家族のことを考え続けることによる疲弊、福祉現場ならではの職場の人間関係での疲弊などがあり、離職率が高い。
- 今後の展望として、虹色畑クラブや居場所「カドベヤで過ごす火曜日」では伴走支援を、小淵沢てこファームではそこでリフレッシュできる対象者を増やしていくことを考えている。
※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません
この記事は役に立ちましたか?
記事をシェアしてみんなで学ぼう