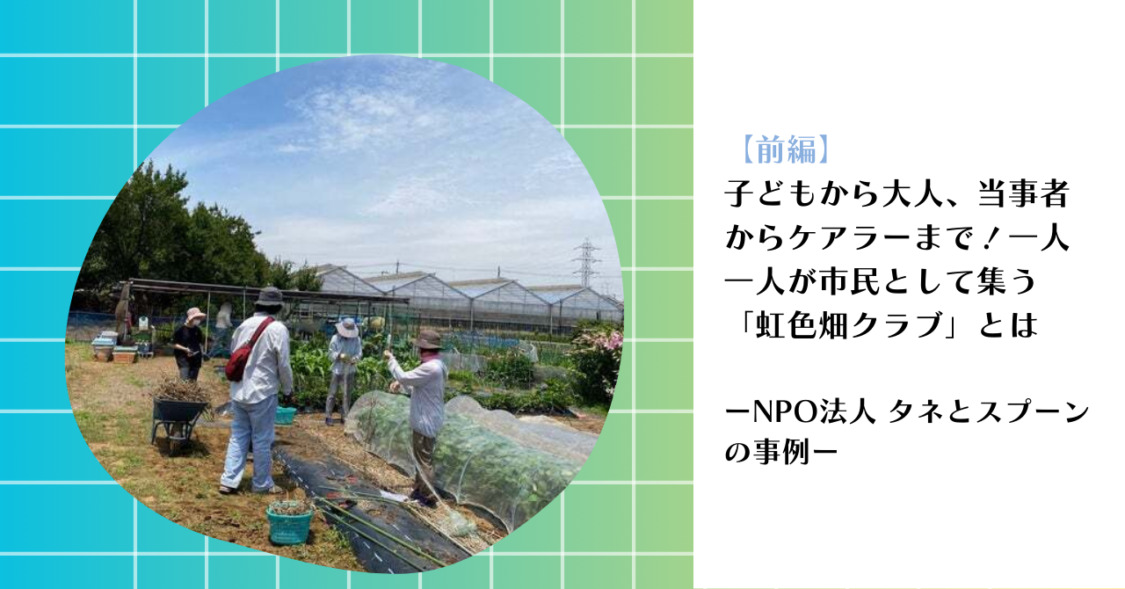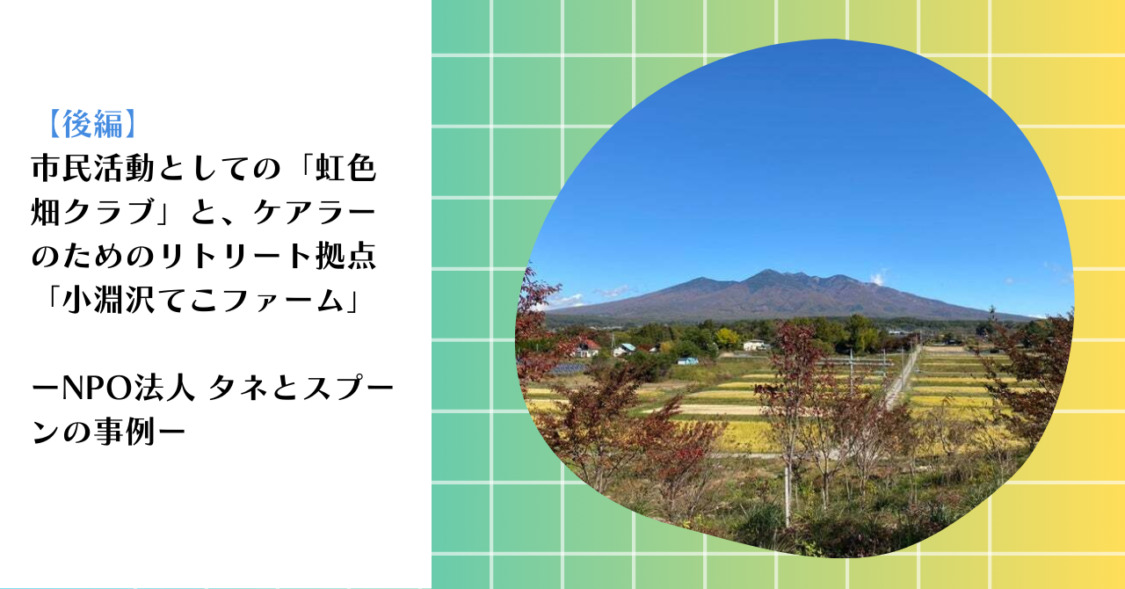NPO法人 タネとスプーン(以下、タネとスプーン)が神奈川県・横浜市で実施する援農活動サークル「虹色畑クラブ」には、子どもから大人まで、心の病や不登校、引きこもりといった生きづらさを抱える人や、そのような方たちを支援するケアラー(支援者)まで、地域の様々な人が集います。
今回は、タネとスプーンの理事長である原田朋子氏に、市民の集いの場として「畑」を選ばれた理由や、年齢・属性を問わず一人一人が1市民として集まる場の醍醐味などについてお話しを伺います。

プロフィール:原田 朋子氏
NPO法人 タネとスプーン 理事長
虹色畑クラブ・小淵沢てこファーム 代表
社会人になってから、企業の仕事についていけないなどの生きづらさを感じ、うつ、発達障害のグレーゾーンなどの診断が出て、一時期引きこもる。その後「成人発達障害と歩む会シャイニング」と出会い、その代表職を経て、2016年に横浜・藤田農園の協力で援農活動サークルをスタート。養育里親の活動も行う。
NPO法人 タネとスプーンの事業について
—まずは、タネとスプーンのご活動について教えてください。
タネとスプーンでは、こちらの3つの事業を行っています。
- 虹色畑クラブ
- 居場所「カドベヤで過ごす火曜日」
- 小淵沢てこファーム
1つ目の虹色畑クラブでは、神奈川県・横浜市にある藤田農園の協力で子どもから大人まで、心の病や不登校、引きこもりといった生きづらさをもつ人や、そのような方たちを支援するケアラー(支援者)まで、様々な人が集まって援農(※農家さんのお手伝い)を行っています。
2つ目の居場所「カドベヤで過ごす火曜日」(以下、カドベヤ)は、神奈川県・横浜市の寿地区(※拠点は横浜市中区⽯川町)で毎週火曜日の夜に開催している居場所事業です。2025年で満15年間続いている事業で、誰かと話したい、一緒にご飯を食べたいと思った人が誰でも参加できる場所で、1時間のワークショップをしたあとに、虹色畑クラブで育てた野菜などを使って料理を作って食べるという二本柱で運営しています。
そして3つ目の小淵沢てこファームは、ケアラーケア、つまり普段は誰かをケアする立場にある支援者たちのケアを目的とした事業です。私の祖父母が残した小淵沢の土地と家を活用して、子ども支援や若者支援、福祉従事者など、さまざまな支援の現場で疲弊してしまっている専門家たちが、現場から離れて気持ちを吐き出したりリフレッシュしたりできる場を作っています。
—もともと虹色畑クラブとカドベヤは、別々の団体で活動されていましたが、なぜ一緒に活動されるようになったのでしょうか。
私とカドベヤの代表の横山さんに共通の知人がおり、その方が「それぞれの理念が同じで、きっと合うと思う」と引き合わせてくださったのがきっかけでした。この時期はちょうどコロナ禍で、行政や公共機関がどんどん閉まっていく中、お互いに踏ん張って居場所を閉めずに運営していました。
コロナ禍は居場所がどんどんなくなったことで、家庭内の問題が悪化して自殺未遂をしてしまう人も出たりと、危機的な状況に陥る当事者が増えました。そんな状況を見て、虹色畑クラブは「やっぱり居場所を無くしてはだめだ」という思いと「畑は屋外の活動だから大丈夫」という思いで運営を続けました。
また、カドベヤも元ホームレスの方や生活保護を受けている方が参加されていました。こうした方はそもそも満足に食事が摂れないので、カドベヤも「週に一回でも手料理を食べさせたい」という思いで閉めずに3年間運営し続けていました。
こうしたコロナ禍を一緒に踏ん張った期間があったので、今後もお互い手を取り合って活動していくために法人化しようという話になり、一緒に活動していくことになりました。
虹色畑クラブの活動について
なぜ「畑」を通した集いの場なのか
—本日は、原田さんが代表を務められている虹色畑クラブと小淵沢てこファームについて、詳しくお話しを伺っていきたいと思います。まず始めに、そもそも虹色畑クラブではなぜ市民の集いの場として「畑」を選ばれたのでしょうか?
原体験は、私の祖父母が畑をやっていて子どもの頃からよく手伝いをしていたことです。その頃から土に触れることが性に合うと感覚的に思っていました。
また、私は社会人になってから一般企業の働き方になじめずに何度もうつ病を発症していて、最終的にその要因として発達障害のグレーゾーンであることが発覚しました。発達障害グレーゾーンだったために一般企業の働き方についていくことができず、うつ病になるという二次障害に20年以上苦しんでいました。
うつ病でアップダウンを繰り返しながらも少し良くなってきた頃に「シェア畑」という市民農園を知り、そこでアドバイザーとして働くことにしたのですが、農作業をする中でやっぱり私は畑が性に合うと再確認できました。そして、それを続けていくと、うつ病で長年苦しんでいた体調がどんどん良くなって安定していきました。
この自分自身の体験から、私と同じように心の病などに苦しむ人にとっても土に触れることはすごく大切なことなのではないかと考え、発達障害や精神疾患の当事者に向けても土に触れるイベントなどができないかと考えるようになりました。
私はその時すでに「成人発達障害と歩む会シャイニング」という当事者と一般市民の交流会をする団体の代表をやっており、その当事者の人達と援農ができないかと考えていたところ、藤田農園さんのボランティア仲間が話をつないでくれ、農作業を当事者と一緒にお手伝いするようになったのが虹色畑クラブの始まりです。

畑の様子(提供:NPO法人タネとスプーン)
—土に触れることが良いというのは、具体的には身体を動かすことや人と一緒に何かに取り組むことが体調に良い影響を及ぼしているということでしょうか?
私が感じた良い点は、農業をすることによって体内リズムが整うことです。
体調が悪いと、たいてい家に引きこもって朝昼晩の時間の流れや季節を感じられなくなってしまうんですよね。しかし、畑に出ると日光を浴びて自然と夜も眠くなります。暑さ寒さも肌で感じられて、身体がちゃんと目覚め始めるという感覚があるんです。
また、時間の流れが止まってしまった当事者にとって、時間が経つにつれてどんどん成長していく野菜は「もうこんなに育った!」という成功体験を得やすいです。野菜が育つ過程を見て、収穫という形の報酬を得て、最後に美味しくいただくというサイクルがとても良いなと思っています。
あと、当事者が参加されるようになってすごく感じるのは、「そこにいるだけでいい」という安心感です。
私は相談支援事業所で働いた経験もありますが、そこでの面談は「話さなければいけない場」なんですよね。しかし、農作業は相手の名前や素性を知っている必要もないし無理に会話する必要もありません。作業内容は難しくないし、失敗してもいい。ただ一緒に作業をするだけでいいというのがとても良いなと思っています。
農作業は、話さなくていいけども一緒に作業して達成感を味わえるという非言語的コミュニケーションのようなものです。一緒に作業したときの思い出ができて、そこから自然な会話に繋がるのも良いところですね。
ちなみに虹色畑クラブでは、畑に来ても来なくてもいいし、来たからといって作業もしなくていいとお伝えしています。そのため、畑に来た人の中にはピクニックシートを敷いて畑での日光浴やお昼寝を楽しむ人もいます。
ケアラーも当事者も、1市民として集う
—虹色畑クラブには本当にさまざまな方が参加されていると思うのですが、参加されている方の年齢層や属性などを教えてください。
虹色畑クラブは赤ちゃんから何歳まででも参加OKで、親子連れや不登校の小学生、20代〜40代の引きこもりや精神疾患のある方、また児童発達や子どもの生活支援、介護などの現場に関わっているケアラーも、サポートメンバーとして参加していたりします。また、地域の60代〜70代のサポートメンバーの方々にも支えられています。
サポートメンバーは、虹色畑クラブの活動の趣旨に賛同してくださった地域の方々です。私がシェア畑で働いていた頃の同僚が多く、農業の経験が豊富なので畑の管理や作業時のアドバイスなどのサポートをしてもらっています。
—ケアラーもサポートメンバーとして参加されているとのことでしたが、こうした方々はどのような経緯で集まってこられたのでしょうか?
もともとは虹色畑クラブに来ている当事者の担当者だったという方もいますが、虹色畑クラブは、普段の現場を離れてケアラーでなくていい場なんですよね。当事者と元担当者が、公式な支援の関係性は終わったけれど、ここでは地域住民同士として繋がっていたりします。
ケアラーの方たちは参加しづらそうにしている方に声かけをしてくださったり、気持ちを吐き出したい方の聞き役をしてくれたり、さりげなく参加者さんの見守りやフォローをしてくれていますが、それは身についているから自然にやっていらっしゃるという感じです。ケアラーとして来ているのではなく、「ここに来るとリフレッシュできる」という気持ちで来てくれています。
また、支援の専門職として働く人だけでなく、引きこもりの子どもをもつお母さん方も参加されています。長年引きこもりだと本人が家から出てくるのは難しいのですが、私はお母さんがリフレッシュするためにお母さんだけでもぜひ参加してくださいとお伝えしています。
以前、母親と一緒でないと行動できない引きこもりの方がいらっしゃったのですが、最初は親子で来ていたものの、途中から子どもは子ども、親は親でそれぞれ別の日に来られるようになりました。
支援する側・支援される側という区別がない取り組みだからこそ、一人ひとりが自分の状態に合わせて行きたいときに行ける場になっていると思います。

畑で実施したチーズフォンデュ会の様子(提供:NPO法人タネとスプーン)
様々な年齢・属性の人たちが集まれるからこその醍醐味
—年齢層も属性も幅広いですよね。その醍醐味は、どのようなところでしょうか?
制度に基づく支援は、年齢や属性で制限がかかることが多いですよね。例えば18歳までを対象とした子どもの居場所があったとして、卒業すると次に繋がる先がなかったり、あったとしても馴染めずに通わなくなってしまうこともあると思います。就労支援も、就職したらそこで支援は終了となってしまう場合が多いです。
そんな時に、何歳から何歳まででも、自分がどんな状況にあっても、いつでも来られる居場所が地域に根付いていれば、ゆるくても繋がりを途絶えさせないことができると思っています。
また、虹色畑クラブの場合、農作業を通しているからこそ他の年代の方とも自然に交流しやすい面があると思います。
同世代と自分との違いを感じて会話に入れない経験をしていたり、同世代とのやりとりを苦手としている子どもや若者にとって、年の離れた60代・70代のゆるやかな空気感をもった人と一緒に過ごすほうが気が楽なこともあります。
また地域のサポートメンバーの方は、日頃発達障害や精神疾患をもつ方などと接点が少ないのですが、虹色畑クラブでの共同作業がその人たちの生きづらさやその人自身の良さを知る相互理解の場になっています。
支援という括りではなく、共に種をまき、共に育てて食べる過程で自然とその人となりを知れるのが虹色畑クラブの醍醐味かなと思っています。
—地域の方にサポートメンバーとして入ってもらう際、発達障害や生きづらさを抱えている人と地域の方との関わり方に難しさを感じる場面もあると思うのですが、そうした課題にはどう対応されていますか?
事前にサポートメンバーの方には精神疾患や発達障害をもった方もいることをお伝えするのですが、同時に「だからといって、特に気をつけなければならないと考えなくてもいい」ともお伝えしています。
なぜなら、私は当事者への配慮はキリがないと思うからです。その方の状況や状態が悪いときには、どんなにケアに努めてもうまくいかないこともあります。特性上NGワードがある場合は共有しますが、それ以外は普通に接しましょうというスタンスです。
作業中には休憩時間が10〜20分ありますが、そこまで会話をする場面がなく、時間も長くないこともあり、変に気を遣ったりすることなくちょうど良い距離感で自然に関わることができているのではないかと思います。
—参加される方はどのように取り組みを知って来られるのでしょうか?
私がかつて若者支援関係の仕事をしていたので、関連する神奈川県・横浜市内の行政機関には、営業をして「社会資源として活用してください」というお話をしました。
虹色畑クラブには社会福祉士がいるので、配慮が必要な方の受け入れができることや情報共有ができることを強みとして、区役所の障害支援課や生活支援センターの障害関係、基幹相談、青少年相談支援センターなどに紹介をお願いしています。そうした支援機関から畑の近くに住んでいる方を繋いでいただくことが多いですね。
あとは、地域のケアプラザで精神保健サロンを運営している団体と連携していて、そこからご紹介いただくこともあります。最近はインターネットで「発達障害」「農作業」といったワードで検索してホームページを見つけて来る方も増えてきました。
まとめ
今回は、NPO法人タネとスプーン理事長の原田さんに、タネとスプーン立ち上げのきっかけや虹色畑クラブでの活動について伺いました。ポイントを以下にまとめます。
- 虹色畑クラブの活動は、原田さんがうつ病で20年以上苦しんでいたところから農作業で回復し体調も安定した経験をきっかけに、近所の農家さんや畑仲間らの協力のもと開始した。
- 虹色畑クラブには、不登校の小学生から20代〜40代の引きこもりや精神疾患のある方、60代〜70代の地域住民やケアラーもサポートメンバーとして参加している。
- 誰でもいつでも来られる居場所が地域に根付いていれば、ゆるくても繋がりを途絶えさせないことができる
- 支援という括りではなく、共に種をまき、共に育てて食べる過程で自然とその人となりを知れるのが虹色畑クラブの醍醐味
後編では、虹色畑クラブを市民活動として実施される理由、またケアラーケア事業の小淵沢てこファームでの取り組みについてご紹介していきます。
※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません
この記事は役に立ちましたか?
記事をシェアしてみんなで学ぼう