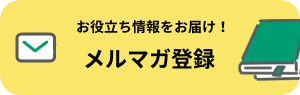2024年3月28日に、認定NPO法人 Learning for All(以下、LFA)と東京大学大学院教育学研究科(以下、東京大学)は、「地域協働型子ども包括支援」の実態・成果を明らかにするべく共同で実施した調査に関する公開シンポジウムを開催しました。
イベントレポート第3回は、LFA代表理事の李 氏と、共同調査の協力者である東京大学教育学研究科 教授の本田 氏、同 准教授の大塚 氏の3名によるパネルディスカッションの様子をお伝えします。
▶過去の連載はこちらからお読みいただけます。

プロフィール:本田由紀 氏
東京大学大学院教育学研究科教授。放送大学客員教授。
専門は教育社会学。教育システムと他の社会システムとの関係およびその変化に関する実証的・理論的研究。主な著書は『若者と仕事』、『多元化する「能力」と日本社会』、『教育は何を評価してきたのか』など。

プロフィール:大塚類 氏
東京大学大学院教育学研究科准教授。
専門は臨床現象学。広い意味での教育実践現場でのフィールドワークに基づき、人々やコミュニティの在りようを描き出す質的研究。主な著書は『施設で暮らす子どもたちの成長』、『さらにあたりまえを疑え!』(共著)『すき間の子ども、すき間の支援』(共著)など。

プロフィール:李 炯植(り ひょんしぎ)氏
1990年、兵庫県生まれ。東京大学教育学部卒業。東京大学大学院教育学研究科修了。2014年に特定非営利活動法人Learning for All を設立、同法人代表理事に就任。これまでにのべ11,800人以上の困難を抱えた子どもへの無償の学習支援や居場所づくりを行っている。全国子どもの貧困・教育支援団体協議会 副代表理事。2018年「Forbes JAPAN 30 under 30」に選出。2022年「内閣官房のこどもの居場所づくりに関する検討委員会」の検討委員に選出。
「居場所づくり」の特徴と、その成果の測り方
大塚:定性のインタビュー調査で興味深かったのが、まず、「居場所づくり」という言葉に関して、「本来居場所は提供されるものではない」という共通感覚が支援者にあり、物理的な居場所を利用者、つまり子ども当人が居場所にしていくのであって、それをサポートするのが支援者なのだとおっしゃっていたことです。
その上で、特徴の1点目としては、利用者の回復や変化などのいろいろな観点で、当人が拠点を居場所にすることには時間が必要であるということです。
今回は、①学習支援拠点②小学生を対象とする居場所③中高生を対象とする居場所の3拠点でインタビューをしましたが、どの拠点の支援者の方も、縦でも横でもないナナメの関係の存在として、本人がどうしたいのかということをゆっくり見守ったり一緒に考えたりする時間を大切にされていました。
例えば、小学生向けの居場所の職員さんは、子どもたちは日常生活の中でしんどい状況に置かれているからこそ、居場所の中では何も心配せずに自分の好きなことが好きなだけできる、もちろん宿題等いろいろやるべきことはあるけど、それでも何も心配せずに自分の好きなことができる、のんびり過ごせるということを保障していきたいという意味で「余白の時間を大切にしている」とおっしゃっていました。
学習支援拠点のインタビューだと、「暫定解を積み重ねる」という言葉が印象的でした。支援者が「これが正しいからこちらに導かなければいけない」と考えるのではなくて「常にこれは暫定的な解答でしかなく、子どもと一緒に時間をかけて、より良い回答みたいなものを考えていきたい」ということを示しているそうです。
中高生を対象とする居場所では、「何もしない」「先出ししない」のように、「何々しすぎない」ということをすごく大事にされていました。支援者が子どもを支援するだけではなく、むしろ居場所では「子どもに返す」とか「子どもに繋げる」という形で、子どもたちが中心となるコミュニティを後方支援・側面支援するという感覚が語られていました。
他方で、当人が「居場所」と感じられるまでに時間が必要であるからこそ、成果が何なのかというのがとても難しい観点になると思います。
特徴の2点目として、どの拠点でもそのつど、拠点の中で可能な範囲でどこまでやれるかということが模索されているのが大変面白かったです。
学習支援拠点の方がお話されていたのは、子どもにとって同世代の子どもたちが複数いるという状況が好ましい場合もあるけれども、しんどい子どもたちにとってはとてもしんどい場になることもあるということです。そうなったときに、学習支援拠点では大人と子どもがマンツーマンで時間を取れる。もちろん勉強する時間は確保するけど、それだけではない。そうやって、同世代の子どもたちと一緒にいることがまだしんどい子に一対一で支援したり、学習支援拠点という枠組みの中で可能な範囲でその子がやりたいことを一緒にやることで、その子たちが個別の大人との関係から、子ども同士のコミュニティに進めるように支援されていたのが興味深かったです。

李:先ほど大塚先生が仰っていた「回復」というキーワードについて、LFAの拠点に限らず居場所に来ている子たちは、虐待などで権利侵害を受けて、自分の声すら自分で聞けなくなって、心も閉ざしてしまっていることがあります。もがきながらそこにいるような子が居場所に来るようになって、自分の声を聞いてくれる場所、物理的に危害を加えられない空間に来て、そこでようやく「自分ってここにいていいんだ」「大人って自分の話聞いてくれるんだ」ということを思えるようになる。そうなって初めて子どもたちは、「自分は逃げたいと思ってるんだ」「休みたいと思ってるんだ」と、自分の感情や本質的要求に気づき始めます。そこでようやく癒されたり、回復をしたりしていくという姿が、居場所に来た大半の子どもに見られます。それはかなりの数ですが、すごく見えにくいものでもあります。ぱっと見て「この子は回復してるな」とわかるようなものではなくて、本当に信頼できる支援者1人にしか見えない何かもあったりするような、そのぐらい「見えにくい変化」というのが実は居場所の本質的なところだったりします。
そういう過程を経て子どもたちは「本当はこういうことやりたかったんだな」「勉強したいんだな」と思えたり、「学校に行けてないから、思い出を作りたい」「こういうところに遊びに行ってみたい」と思うことに繋がっていきます。1週間などの短期間で起こる話ではなくて1年とか2年、あるいは3年4年かけてそこに辿り着く子たちもいます。なので何が成果なのか非常に難しいと改めて思いますが、そういったところに寄り添っていきたいと考えています。
もう1つ重要なのが、我々支援者がお子さん1人1人を見ている、個別で見てるという点で、「集団として動かそう」というのはあんまり考えないんです。個別で子どもを見て、そしてその集合体として居場所があるというような、少し形をつかみにくいところも1つポイントかなと思っています。
本田:定性調査において、子どもたちにとっての居場所の価値を3点に整理していただいていますが、その中で「気を遣わずに話を聞いてもらえる場所」とまとめられてます。それを価値だと感じているということは、これまでずっとずっと何かに気を遣い続け、自分を追い込み続けて、話を聞いてもらえなかった子たちであるということの裏返しだということです。「参考になるな」とか「横にいてくれるな」という関係を持てる大人が、おそらく家庭にも学校にもほとんどいなかった。そういう子たちは、NPO等の組織に相談するのにも苦労するぐらい、すごくマイナスなところから出発している。そのマイナスの部分をゼロまで持っていくために、ある意味そこまで環境がひどくない人であれば当然に得ているようなものを、ボコっと窪んでいるところをそっと埋めるための場所として居場所があるのだろうなということを痛切に感じた次第です。
また本調査において、3年前と比較して何が起こってるかも見ようとしました。3年前というとコロナもあったり、3年の間に対象の子どもたちが自然に3年分成長していることもあって、これが拠点の成果であるかどうかの断定は全くできませんが、その子たちの状況の改善と悪化を比べると、改善の方が少し多く出てきているという結果に、本当にかすかな希望のようなものを抱いています。ですから、居場所の価値の測り方ということはこれぐらい繊細な事柄なんだということが、定性調査でも定量調査でも明らかになったかなと思います。
最近は、「成果を目に見える形で示しなさい」という圧はとても強いですが、実際にその対象者が必要としていることは、傷つけられたマイナスからの回復、少しずつゼロに持っていくような場なのであって、そこで何が子どもたちの中で起こっているかということは、定性でも定量でも本当につかみにくい事柄であるということを申し上げておきたいと思います。
子ども支援における地域との連携の必要性と今後の課題
李:まず地域連携の必要性ですが、子ども1人を支えるというのは、多機関連携が前提です。例えばうちに来ているお子さんたちは、勉強のニーズもあれば生活支援のニーズもある。子どもが抱える困難は複合的で、かつ家庭を見ても、色々な制度に紐づいて経済的な支援を受けていたりだとか、すでに色々な大人が関わっているわけです。子ども1人を支えようと思ったら、地域、広く見ると行政や学校や地域、他のアクターと連携せざるを得ないということがあります。
その中で連携することでどんな良いことがあるか、どういうふうに連携しているかという話をすると、LFAの場合はそもそも地域と連携してるから子どもが来るんです。我々がやってるこの拠点(※本調査の対象となった拠点)は自主事業なので、行政の委託事業ではありません。そのため、生活困窮の方全員にチラシを配るとかはできませんので、いろんな方に「こういう困りごとがある人がいたらうちの団体を紹介してね」と紹介をお願いしていますが、これが実はすごく難しいんです。そもそも困ってる人の声を聞いても聞き流して終わってしまう人が多いですし、支援先を知らない人も多い。学校の先生が近隣の子ども食堂や学習支援拠点を知らなかったり、生活保護のワーカーさんは基本的に親に対応してますから、子どもにはあんまり目を向けてない。なので生活保護のワーカーさんが子ども支援に関わってることは実は少ないんです。そういう中で我々は普段からいろんな方々、行政や学校の方々と顔見知りになって、連携関係を作って子どもを繋いでいただく関係を作っています。
平時からそういう関係づくりができてると、例えば虐待が起こった際には、通告をして関係機関と役割分担しながら早期に対応ができます。学校と保護者だけだとうまくいかなかった何かを、第三者の我々も含めて相談してもらえるような関係性があるので、保護者と子どもの関係性が変わるということもあると思うんです。いろんな人のSOSを見逃さずに、みんなで支え合いながら、早期に必要な支援に繋ぐことができるような地域を目指してやっています。
一方で、民間と行政が連携することは良いことではあるものの、非常に重篤なケースについては行政の方でやった方がいいんじゃないかと思うこともあります。民間と行政とが対等な立場で、お互いの役割分担をしながら進めていく関係性をどう今から作っていけるのかが今後の課題かなと思います。

大塚:今回の定性調査の結果として、ソーシャルワーカーを中心として、地域の中で個別のお子さんの支援に必要な連携を十分取れているという印象がありますし、語りからもそれが読み取れると思います。ただ、子ども家庭支援センターや区、学校、病院、警察などとの連携は十分に取れているものの、それぞれの拠点が設立されて5年ほどなので、まだそんなに歴史が長くない。そういう意味で更なる連携や展開が必要だということは、支援者の皆さんが語られていました。
またソーシャルワーカーさんのおっしゃっていたことで印象的だったのが、「苦労を奪わない」という言葉です。例えば、中高生向けの居場所の場合、高校を卒業したらLFAの居場所は卒業することになります。もちろんOBとして帰ってこられたりとか、フードパントリーのお手伝いをされるというような形で関与できる余地は残されていますが、「利用者」という枠からは外れる。LFAを離れた後も、利用者の多くはその地域で暮らしていくので、LFAの居場所を利用している間に地域とどう繋いでいくのかということが重要な問題として浮かび上がっていました。その際に、「地域住民にボランティアをしてもらうだけではなくて、拠点や子どもたちが地域住民に何か返していけるような、お互いに意義があるような関係性を作りたい」ともおっしゃっていました。
本田:地域連携や地域との関係といっても、かなり多義的に「地域」という言葉が使われているなと感じました。例えば、地域という言葉が、色々なものを寄付してもらったりとか、イベントにお互いに参加し合ったりするような近隣住民のことを指していることもあれば、行政が管轄する、まさに行政組織・自治体ということを暗に意味していることもあります。あるいは行政だけでなくて、同じ公共的な空間の中にある別の団体や機関とのWeb上の関係性という意味で地域という言葉が使われることもあります。地域連携を考えるときには、まず言葉の整理が必要だと思います。
また地域のいろんな機関間のネットワークなどもすごく重要なことだと思うんですけれども、たくさんの機関があればあるほど、その間を結んでいくことは大変な苦労ですし、難しい。組織によって、あるいは人によって、「どこと連携したいか」「どこが連携の中心のハブになるか」の問いの答えが、羅生門的に全く違う。同床異夢のように、みんなが違う「子ども支援」や「連携」のイメージを持っているという状況が、調査結果から明らかになってきました。いろんな自治体の子ども支援・若者支援の状況を見させていただくのですが、結局のところ、「〇〇さんなら信じられるから紹介しよう」というような、人づてのネットワークが取り結ばれているような場合も珍しくないように見えます。もしその方が体を壊されたりして活動を辞めてしまえば連携が切れてしまうような状況が多い中で、もっと安定的な体制をシステムとして何とか作っていけないものかと思います。
そして子ども支援であれば、その責任を担っているのは自治体ですし、子どもと日々関わっている学校という場も無視することはできないと思います。皆様ご存知のように、今の学校というのは、先生方が本当に忙しい。教育内容がとてつもなく増え、学校統廃合によってたくさんの子どもが1つの学校に押し込められたりと、学校そのものが本当にきつい状況になっています。そんな中で、子どもの数は減っていってるのに、不登校や自殺の件数は鰻のぼりに上がっている状況にあります。つまり学校というものが子どもを支え育むどころか、「もうここではいらない」って逃げ出してしまう子どもを日々量産してしまいかねない場になっているのであれば、まずはそこの是正をどうしていくかということを最優先して考えなければならないのではないでしょうか。そういう苦しい子どもたちを生み出さないために、子どもが毎日のように通い、長い時間を過ごしている学校の平常の体制をどのような方向に持っていくのかということも、地域における支援の連携と並行して考える必要があるのではないかなと思います。
今回の調査を踏まえた課題と今後の発展の展望・可能性
本田:今回の調査は、単に1団体の実績報告書のような形でやるのではなくて、8つの団体に調査に参加していただいて、多くの地域での実態を明らかにしようとした点が非常に魅力的でした。
私は定量調査の方に関わらせていただきましたが、苦しい状況にある子たちの傷口に手を突っ込むようなことはできないため、支援団体が持っている子どもの情報を後からデータとして挿入する、あるいは保護者の情報と子どもの情報を繋ぐといった手法で、最終的には補い合って関連を分析する構想のもとで設計していましたが、蓋を開けてみたら、そのようなことが可能になるケースというのは極めて少なかったことが、今回痛感している反省点です。
今回は支援現場を持つLFAと協力させていただいて、研究機関単独でやるのと比べれば多少力が入った状態にはなったかと思いますが、それでもこれだけの限界がありました。これから国としてエビデンスベースドポリシーメイキング(注1)を強化していくのであれば、こども家庭庁やその他の省庁にも、こういう苦しい子どもたち・支援団体の実情についてしっかり把握していただきたいと思います。
(注1)証拠に基づく政策立案。政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすること。
そしてこのような調査はお金もかかります。私どもも、今回の反省に基づいて今後も調査をやっていこうとしていますが、より大きな枠組みで実態を把握していくことが必要ではないかと思っております。

大塚:定性調査は大変ミクロな調査ですが、そういった調査も大規模な調査と並行して丁寧に行われるべきだと思っております。今回の調査の限界としては、時間の制約もあって全てのインタビューを1回しかできなかったこと、それから支援者の方にも私達がより一層信用される必要があるということが挙げられます。
利用者インタビューに関しては、結局3人しかインタビューができませんでした。インタビューへの参加を強制されないという点ではその拠点らしくて素敵だなと思いつつも、やはりすごく少ない人数しかインタビューできなかったのは残念でした。もし来年度以降も調査を続けることができるのであれば、もちろん信頼された上でという条件がつきますけれど、中高生や小学生の子どもたちにも、インタビューという形でなくても、何らかのお話をする中でニーズを聞きたいと思います。成果となったときに、ミクロな視点から、その利用者がどう満足するのかや、何を求めてるのかということをきちんと捉えることは大事だと思うからです。
また、現場の中で育まれている「支援者の専門性」についても見ていきたいなと思っていたのですが、定量調査からは、支援者の皆さんがその点には「満足されている」という結果が出ていました。拠点イズムのようなものは属人的なのかなと思いきや、そうではない形で緩やかに継承されていているのではないかと推測します。おそらく背中を見て育つ形で、支援者がコミュニティの中で一緒に過ごす中で、「あの人はああいうふうに答えるんだ」とかを学ばれている。今後はそういう部分をきちんと描いていきたいと考えています。また、「この人だからできる」という属人的な範囲を超えていく可能性が、現場の中で背中を見て育つ支援者の専門性の中にあるのではないかなと思います。
李:今回の調査は東京大学とLFAの共同研究であり、またゴールドマンサックスさんがスポンサーをしてくださっています。現場をやってるNPOと大学の研究に民間の資金が入って調査をするという事例はなかなかなく、すごく重要だと思いますので、できるだけ長く続けばいいなと思っています。
また、これからこの調査をどう使っていくかについては、他の団体さんにどんどん情報を提供していきたいですし、今後も協力してくださる団体さんがいれば、その団体さんの良いところを全国に発表していきたいと考えています。こういう調査を通じて実態を明らかにすることで、共通言語が増えたり、団体間の学び合いが増えたり…変に奪い合う関係ではなくて、みんなで手を繋いで日本の子どものために地域社会を良くする仲間作りができないかという想いは当初からありましたし、こういう可能性はどんどん伸ばしていきたいと思います。調査に入っていただくことでいろんなフィードバックをいただけることも現場にとってすごく良いことだなと思っているので今後も行っていきたいです。
一方で、LFAが頑張り続ける地域社会でいいのか、その再現性はあるのか、そういったところをきちんと見極めて議論をして、国や地方自治体にアドボカシーや政策提言をしていくようなことも重要かなと思います。お子さんの対応は、国や基礎自治体で責任をもってやるべきだと思いますし、それに関する予算案を求めていく動きも、子どもたちの権利を代弁する立場として我々のような支援団体が担うべき役割だと思いますので、継続してやっていきたいです。
この記事は役に立ちましたか?
記事をシェアしてみんなで学ぼう