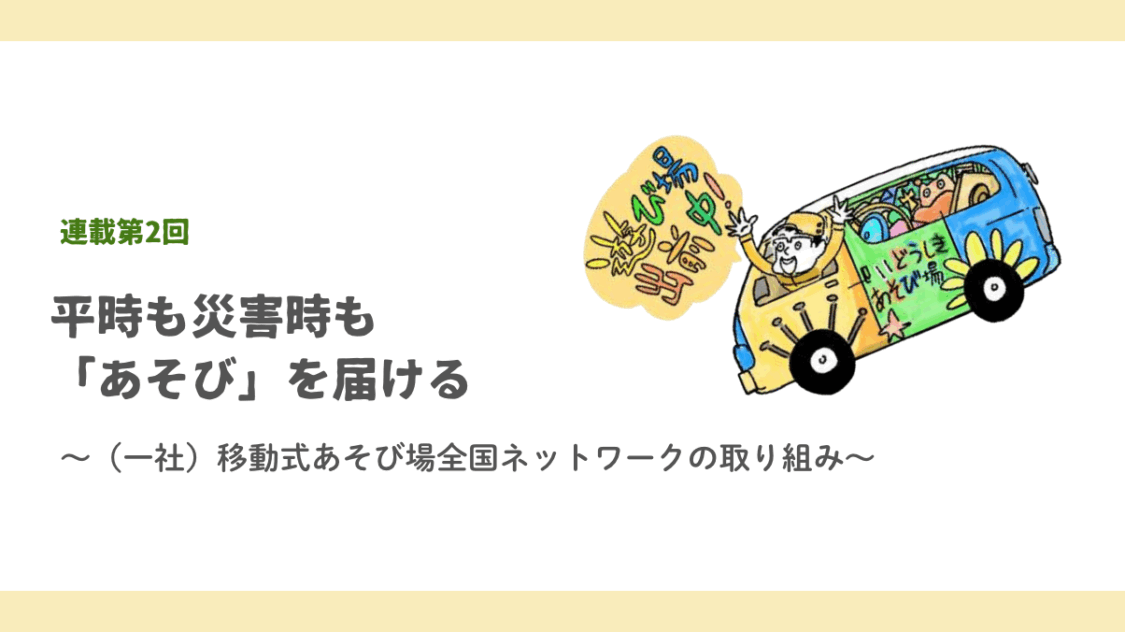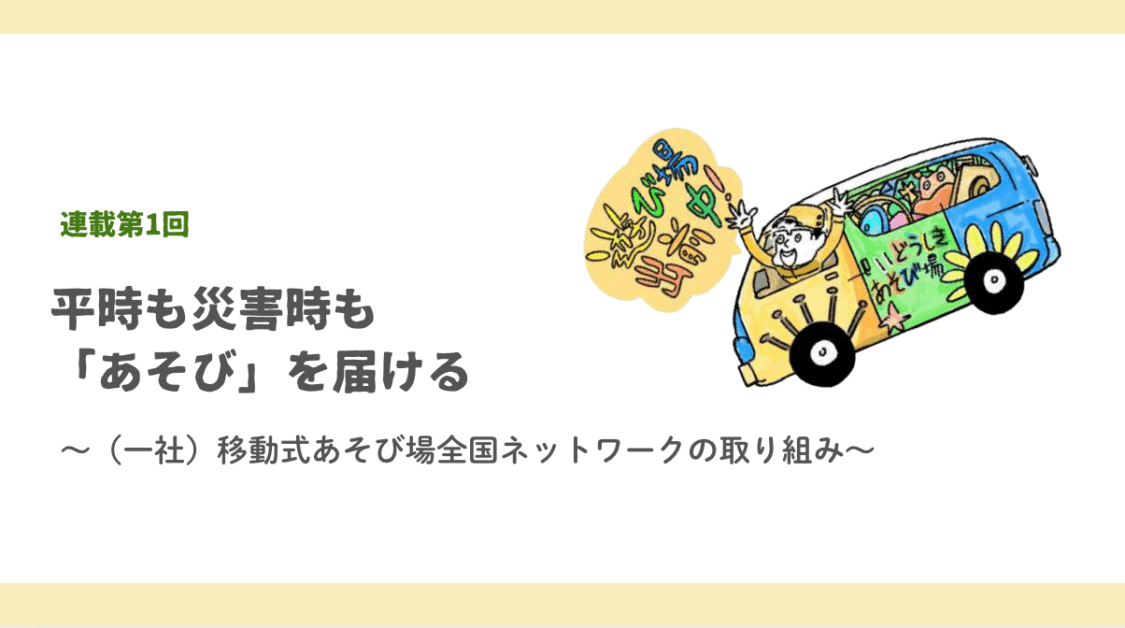近年、大きな災害が増えたり猛暑が続いたりと、子どもたちが自由に外で遊ぶのが難しい状況が続いています。とりわけ、安心して過ごせる「あそび場」が少ない地域では、体験格差や子どもの居場所の喪失が深刻な課題となっています。
そんななか注目を集めているのが、あそび道具を載せた車=プレイカーで全国を巡り、子どもたちに多様なあそびを届ける「移動式あそび場」という取り組みです。全国では25~30台が稼働し、これまでに私は全国で延べ42万人以上の子どもたちと出会ってきました。
この活動を創設し、「あそびを待つのではなく、自ら届ける」ことを25年間続けてきたのが、一般社団法人移動式あそび場ネットワークの代表理事であり、プレイワーカーの星野諭さんです。
第2回では、被災地での活動を通じて見えてきた「あそびの力」と、地域主体の支援のあり方についてお話しいただきます。
第1回はこちら:
関連記事はこちら:

プロフィール:星野 諭 氏
プレイワーカー/一級建築士/こども環境コーディネーター。1978年新潟生まれの野生児。高校から子どものボランティア活動を行い、2001年の大学時代にNPO団体設立。子どもの居場所づくりや地域イベント、環境共生デザインやキャンプ、廃材あそび場やフリースクールなどを実施中。2008年に移動式あそび場を創造し、大都市部や里山、被災地など全国で活動を展開している。
被災地支援への原点・中越地震での気づき

画像提供:移動式あそび場全国ネットワーク
—星野さんは2008年にプレイカーを作る段階から、災害支援を想定されていたそうですね。
はい。車を作る時点で「日本では必ず大きな地震が起こる。子どもたちが被災地で居場所を失い、遊ぶ場所がなくなる。だからこそ、すぐに駆けつけられる仕組みを作ろう」と強く意識していました。助成金申請の企画書にもその思いを盛り込み、平時から防災を想定した装備や準備を行っていました。
その背景には、2005年の中越地震での体験があります。新潟出身の私は、長岡での大地震の際に現地に入りました。仮設住宅であそび場を失った子どもたちを見たとき、「ここにあそび場がつくれたら、子どもたちはもう一度元気を取り戻し、生きる力を取り戻せるかもしれない」と感じました。
特に、被害の大きかった山古志村の子どもたちの姿は深く心に残り、あそび場を届けるアイディアにつながったのかもしれません。
—災害支援において「あそび」の優先順位をどのように考えていますか?
これがとても難しいところで、生きていく上で「食べる・寝る・トイレ」といった基本的なことが最優先とされ、子どものあそびや居場所づくりは「後まわし」にされることが多いです。
しかし、子どもたちにとって、あそびは「生きる力」そのものです。あそびは本質的で本能的な営みであり成長の原点であるにもかかわらず、その価値は十分に理解されているとは言えず、今もなお課題だと感じています。
「あそびは生きる力」を実感した石巻での10年間

画像提供:移動式あそび場全国ネットワーク
—東日本大震災では具体的にどのような活動をされたのですか?
宮城県の石巻を中心に、福島も含めてあそび場を運営するための人材支援を行いました。石巻へは150回以上通い、10年間にわたり支援を続けました。現地では私たちが前面に立つのではなく、「支援者を支える」という意識を大切にしていました。地域であそび場を担う人を育て、持続可能な仕組みづくりに注力したのです。子ども一人ひとりの声を聞き、外部から来た人間だからこそできる役割を意識して関わっていました。
—特に印象的だったご経験があれば教えてください。
2011年9月、4歳の女の子がたまたまあそび場に立ち寄りました。お母さんによると、その子は津波のショックでお風呂もトイレも寝るときも、6カ月間ずっとお母さんの手を握ったまま離せなかったそうです。この日も1時間以上ずっとお母さんに抱きついていました。
ところが、積み木やピタゴラ装置のコリントゲーム(釘や輪ゴムを使って仕掛けを作り、玉を転がして遊ぶ手づくりのゲーム)に夢中になるうちに、ふとお母さんから離れてあそび出したんです。お母さんはもう、号泣していました。嬉しさと今までのストレスが入り混じった涙だったと思います。
改めて「あそびの力」と「移動式で駆けつける意味」を強く感じました。たった一日、一瞬の出会いでしたが、「あそびの力」で、お母さんの心も、子ども自身もトラウマを一歩乗り越えることができた。この体験は、今でも忘れられない大切な思い出です。
—被災地で子どもの「遊ぶ力」について感じたことはありますか?
子どもたちは本当にどんなものでもあそびに変えてしまいます。がれきを「まちの記憶」と呼んで集め、それを再利用してみんなで公園を作ったり、プレーパークを開いたりしました。釘を抜き、再利用して、廃材だけであそび場を作る。戦後直後の日本のような光景でした。
一度、支援物資で届いたゲーム機を配るかどうか、地元の人たちが困ったという話を聞いたことがあります。
実際に配ったところ、避難所の室内からでなく、子どもたちは1週間あそび場に来なくなりましたが、結局飽きてまた戻ってきたそうです。
その経験から「被災直後にゲーム機って本当に必要だったのか?」という問いが生まれました。むしろ、段ボールがたくさんある方が、壊したり作ったりと工夫しながらより創造的にあそび、交流していたのです。
「本当に必要なものは何か」を考えるきっかけとなった出来事でした。
能登半島で実践する「地域主体」の支援

画像提供:移動式あそび場全国ネットワーク
—現在進行中の能登半島地震での取り組みについて教えてください。
能登では現在、2台のプレイカーが稼働しています。1台目は、子どもたちと一緒に作った「ジンベイ号」。1年目は、20〜30の外部団体や個人が週3〜4回のペースであそび場を運営し、現地に車を置いて支援者が電車で通う形をとっていました。
2年目からは現地のお母さんたちにノウハウをシェアして、お母さんたちが主体的に運営するスタイルに移行できました。今年4月からは、この地域主体の形で動いています。
—なぜ「地域主体」への移行を重視するのですか?
外部の支援者がプレイヤーになってしまうと、支援者がいなくなったときに活動が継続できなくなるからです。現地の人が子どもたちの相談相手や地域のコーディネーターとして機能しないと、持続可能な支援はできません。
だからといって、それを強いてしまうと負担になるから、そのバランスが大切です。現地の人と一緒に考え、物やノウハウ、資金を共有し、できる人ができることを少しだけ頑張ること意識しています。能登では、今後5年間は必ず支援を継続する予定です。特に半島の奥の方に行くほど地震の影響が残り、子どもたちが自由に外で遊べない状況が続いているので、移動式あそび場の役割はまだまだ大きいです。
被災地支援で学んだ「コミュニティを調整する」ということ
—被災地で活動する上で苦労されたり、工夫されたことはありますか?
石巻の仮設住宅では、子どもの声が「うるさい」と注意されることがよくありました。公園が潰されて仮設住宅になっていたので、子どもたちは行き場所がなく、駐車場をあそび場にしていたため安全上の問題もありました。
そこで、屋内で子どもたちが遊んでいるのと同じ時間に、おじいちゃんおばあちゃんとお茶会を開くことにしました。
無理に交流をうながすのではなく、子どもたちと地域のおじいちゃんおばあちゃん、コミュニティの人たちが自然にゆるくつながれる、ちょうどよい距離感を大切にしました。お茶をきっかけに「一緒に飲もうよ」と声をかけ合いながら、毎週少しずつ関係を深めて行ったのです。
—このご経験は平常時の子ども支援でも活かせそうですね。
コミュニティの課題は一朝一夕には解決しません。時間をかけて信頼関係を築く「時間のデザイン」が大切です。都市部でも「公園で子どもがうるさい」と言われることはあります。普段から地域の人たちとゆるやかな繋がりをつくっておくことが、摩擦を減らす鍵になると思います。
まとめ
今回は、被災地での活動を通じて見えてきた「あそびの力」と、地域主体の支援のあり方について伺いました。ポイントを以下にまとめます。
- あそびは「生きる力」を支え、災害時に子どもの回復力を支える重要な要素
- 子どもは創造的な存在であり、限られた環境や資源でも豊かなあそびを生み出す力を持っている
- 外部支援者は「プレイヤー」ではなく「支援者支援」の立場で現地の人材育成を支える
- 地域主体への移行を前提とした支援設計が、持続可能な復興につながる
- コミュニティとの摩擦は「ゆるやかな繋がり」「時間をかけた関係構築」で解決できる
第3回では、防災とあそびを組み合わせた革新的な取り組みや、全国100台のプレイカーネットワークという今後の展望についてお話しいただきます。
※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません
この記事は役に立ちましたか?
記事をシェアしてみんなで学ぼう