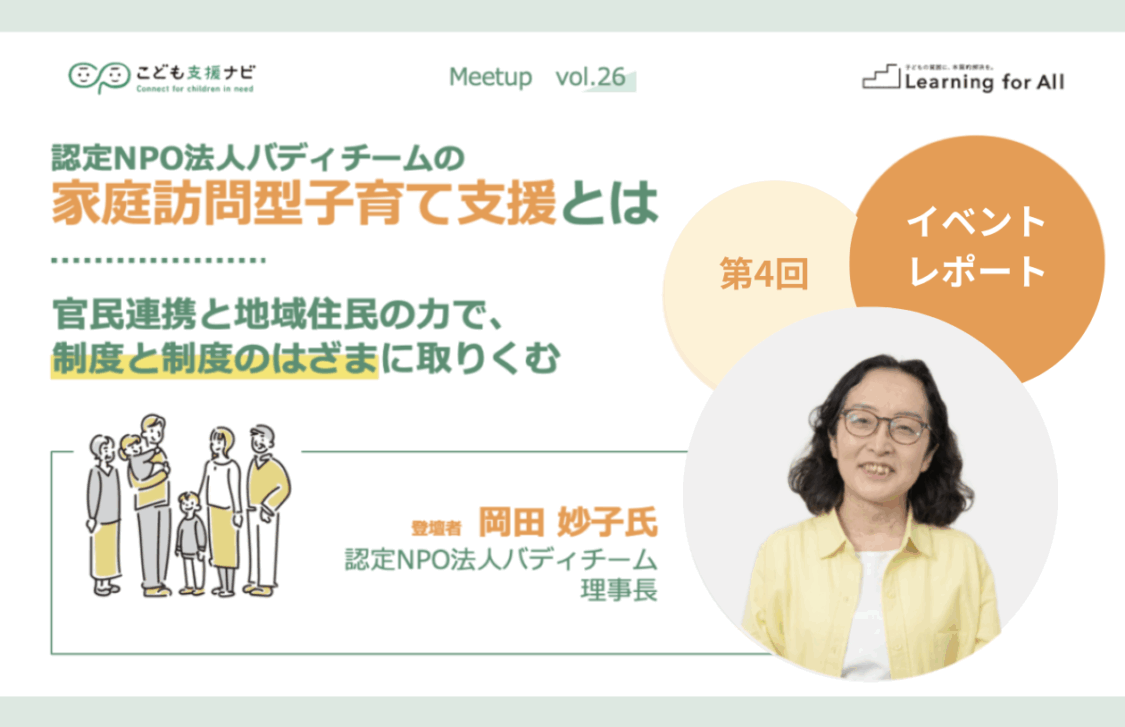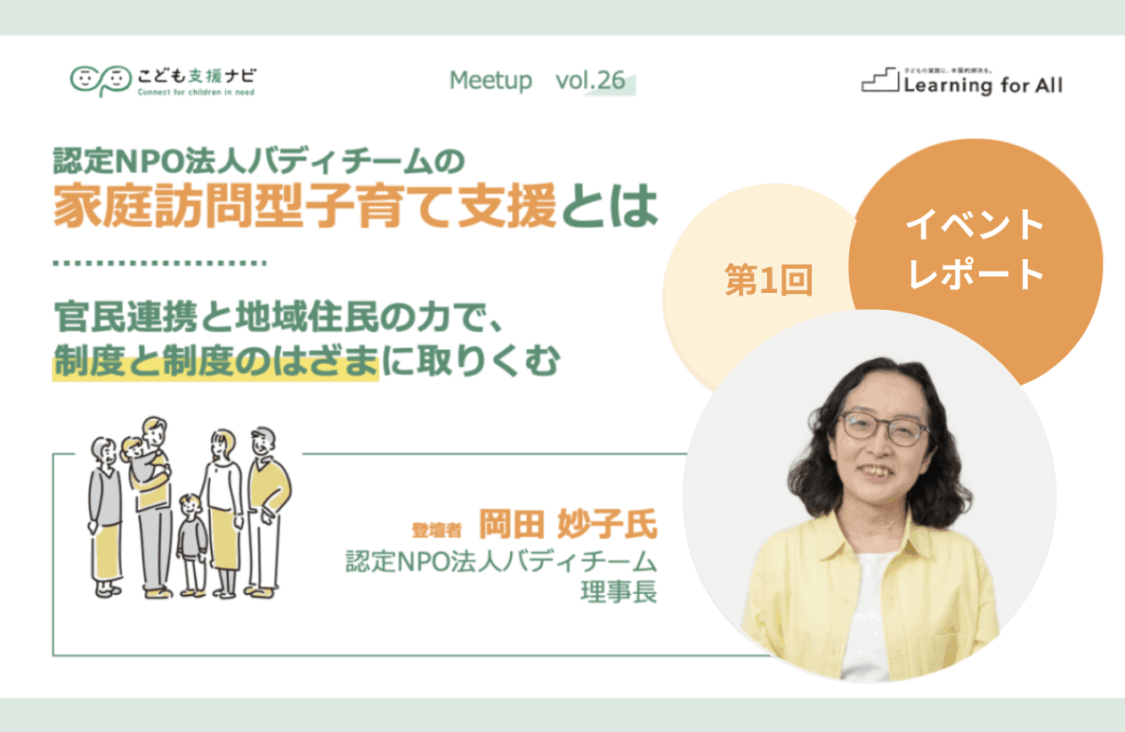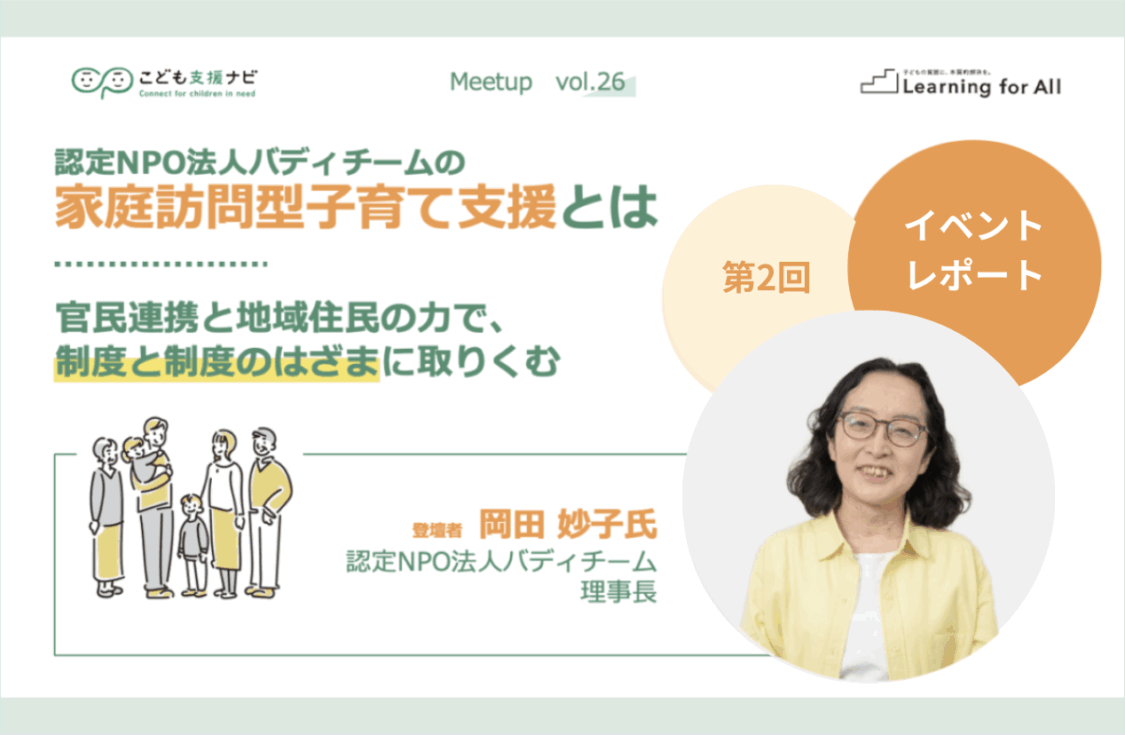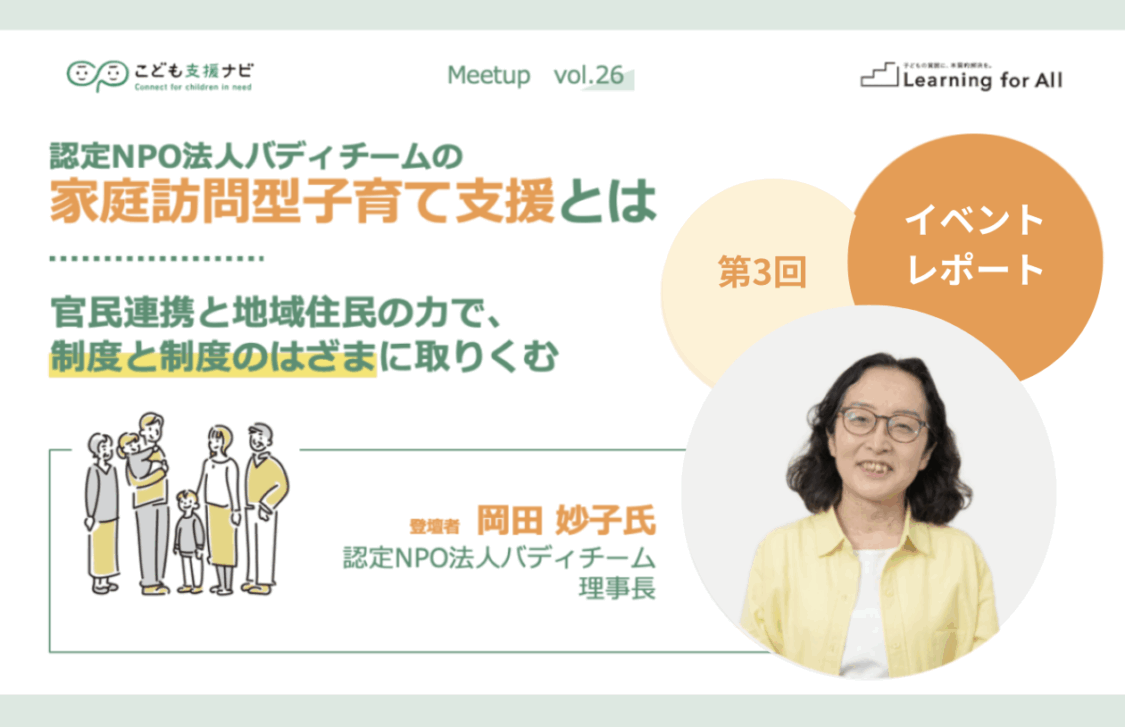2025年6月10日に、子どもに向き合う全国各地の支援者が学び/知見/意見をシェアするオンラインイベント「こども支援ナビMeetup」の第26回が開催されました。
今回は、認定NPO法人バディチーム(以下、バディチーム)の理事長である岡田妙子氏をお迎えし、「家庭訪問型子育て支援とは──官民連携と地域住民の力で、制度と制度のはざまに取り組む」というテーマで、制度に乗りきれない家庭へのアプローチや、地域を巻き込む支援のあり方についてお話しいただきました。
イベントレポート最終回では、参加者からの質問を通じて、家庭訪問型支援の実践における課題と解決策について詳しく探っていきます。
連載第1回・第2回・第3回はこちら:

プロフィール:岡田 妙子氏
認定NPO法人バディチーム 理事長
精神科看護、音楽療法、企業の健康管理などの医療・健康関連職を経て、2007年NPO法人バディチームを設立。
行政との協働(委託)による「支援が必要な家庭への訪問支援事業(子育て世帯訪問支援事業など)」「食の支援事業」「里親家庭支援事業」、自主または民間機関との協働による「制度の狭間」にある家庭に対する訪問支援事業・小さな居場所(ばうむ)事業 などを展開している。

プロフィール:八名 恵理子 氏
認定NPO法人Learning for All 居場所づくり事業マネージャー
大学卒業後、人事・組織系コンサルタントを経験したのち、2021年にLFA入職。入職後は「こども支援ナビ」の運営を担当。2022年度から子ども支援事業部にて、居場所づくり事業マネージャー。小学生中心の居場所、中高生向け居場所の2拠点を担当。
支援はいつ終わるの?再開もある?
—支援の終了はどう判断するのですか?
岡田)制度の支援は、開始時に「どのような目的で、どのくらいの期間行うか」という計画があります。ただ、実際には状況が変化することも多いです。
支援を終了したご家庭でも、再び支援が必要になれば再開する場合もありますし、「次は別の制度へ引き継ぐ」といったケースもよくあります。
支援は「一度で終わるもの」と考えず、柔軟に継続できることが大切です。
—運営費の確保はどのように行っていますか?
岡田)実のところ、毎年が綱渡りです(笑)。制度事業では、自治体によって条件や金額が異なるため、毎年交渉が必要になります。
委託事業だけでは成り立たないことも多く、複数の委託事業・自主事業・寄付などを組み合わせて、なんとか運営しています。寄付を募集しています。
自治体へのアプローチは?
—市民団体として訪問支援の開始を自治体に働きかけるためには何ができますか?
岡田)最近、日本総研がこども家庭庁より委託を受けて実施した調査研究の中で発行した「子育て世帯訪問支援事業 市町村向けポイント集」がとても参考になります。イラスト付きで具体的な始め方が示されていて、「ひと家庭からでもできる」「まずはやってみよう」という姿勢がわかりやすく伝えられています。
まずはこの資料を自治体に見せるのがおすすめです。加えて、小さな実績があると信頼に繋がるので、私たちの中間支援でもそうした団体さんを後押ししています。
拒否的な家庭へのアプローチは?
—家事支援すら断られる家庭にはどう対応するのでしょうか。
岡田)そうしたご家庭は少なくありません。最初は「育児が大変では?ヘルパーを入れてみませんか」と提案してスタートしますが、やはり家に人が入ることに負担を感じたり、警戒されることも少なくありません。
よくあるのが「学習支援ならOK」というケースです。保護者は支援に消極的でも「子どものためなら」と受け入れてくださることがあります。
家庭ごとに何が入り口になるのかを探りながら対応しています。
また「支援する/される」という関係ではなく、一人の人として向き合うことを心がけています。現場支援者の皆さんも自然体で関わってくださるので、難しい家庭でも信頼関係が築かれています。
—各家庭のニーズの見つけ方は?
岡田)まずは話を丁寧に聞くことに専念します。無理をせず、信頼関係を築くことが最優先です。
特に自主事業では関係機関と連携し、「今なら支援を受け入れてもらえそう」というタイミングを見極めることもあります。
マッチングとリスク管理
—訪問支援者と訪問家庭のマッチングはどのように行っていますか?
岡田)コーディネーターの経験と職人技のようなところも大きいですね。支援者のスキルや特性を確認しながら、「この方ならこの家庭に合うだろう」と考え、支援者と家庭の相性を見て、無理がないよう調整しています。
—支援者の安全面の確保のためにはどのようなことを行っていますか?
岡田)リスク対策は徹底しています。事前にコーディネーターが家庭に訪問して状況を確認し、初回も現場支援者に同行します。支援中に異変があれば、支援者から事務局にすぐ連絡できる体制を整えています。支援者が一人で判断せず、必ず事務局に相談するようにしています。
—なぜ連絡先を交換しないのですか?
岡田)過去に、制度終了後も個人的なやり取りが続いてトラブルになったことがありました。困難な状況にある家庭に対しては、個人で責任をとるようなことは難しく、みんなで対応していくことが必要になります。現在は「すべての連絡は事務局を通して」と徹底しています。
子どもの声をどう拾う?
—子どもの気持ちはどうやって拾い上げていますか?
岡田)子どもの年齢にもよりますが、家庭訪問型支援の現場では、どうしても保護者支援が中心になります。だからこそ、子どもの声に意識的に耳を傾ける工夫が欠かせません。
自主事業の方から「今の気持ちシート」などのツールを活用し、子ども自身の気持ちや関心ごとを受け止めるようにしています。
—不登校家庭への支援に入ることもありますか?
岡田)学習支援として関わりますが、目的は学力向上ではありません。話し相手になったり、好きなことを一緒にやったりしながら、少しずつ「やってみたい」という気持ちを引き出していきます。
守秘義務と地域支援者の信頼
—地域の支援者による守秘義務はどう担保されていますか?
岡田)誓約書を交わすほか、ヒヤリハットの共有も欠かしません。「あれ?」と思うことがあればすぐに声をかけ合うようにしています。
官民連携において「個人情報の壁問題」が課題とされていますが、20年近く活動してきて、地域住民の方であっても重大な守秘義務違反は一度もありません。仕組みを整え、支援者を信頼し、責任を持ってもらうことで、意識が自然と育っているのだと感じます。
まとめ
今回は、バディチームの実践から、家庭訪問型支援の課題とその解決策を伺いました。ポイントは次のとおりです。
- 支援は状況に応じて柔軟に終了・再開し、運営費は事業と寄付を組み合わせて確保。
- 自治体には小さな実績と情報提供で働きかけを行う。
- 支援に対して拒否的な家庭には、子どもへの学習支援から入るなど、家庭ごとに何が入り口になるのかを探りながら対応する。
- 支援者とのマッチングと安全対策は、事務局コーディネーターが徹底して行う。
- 子どもの声に耳を傾けることや守秘義務への配慮も忘れず、信頼に基づいた支援を心がけている。
※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません
この記事は役に立ちましたか?
記事をシェアしてみんなで学ぼう